Web・ITエンジニア向け|職務経歴書の書き方完全ガイド【2026年最新版】
2025/08/29
エンジニア3年目で「向いてない」と感じるのはなぜ?レベル・スキル・転職の判断基準
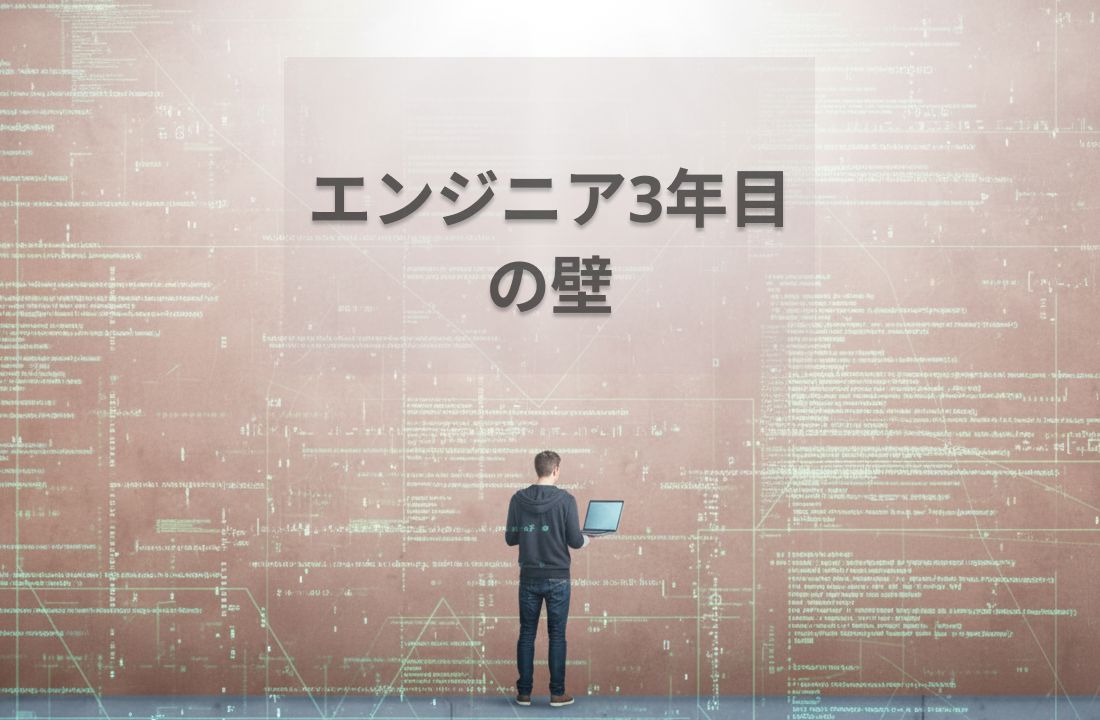
Last Updated on 2025年11月17日 by idh-recruit
「最近、自分だけコードを書くのが遅い気がする」
「上司の期待に応えられない」
「設計レビューでも話についていけず、向いてないのかもしれない……」──そんな風に悩んでいるエンジニアのあなたへ。
キャリアの根幹が揺らぐような不安を感じながら、現場で踏ん張っていませんか?
でも、ちょっと立ち止まって考えてみてください。3年目まで続けてこられたエンジニアであるということは、まったく向いていないわけではないはずです。実は、今あなたが直面しているのは、「仕事のフェーズ」が変わったことによる戸惑いかもしれません。1〜2年目とは違い3年目を迎える頃には、要件整理や設計、顧客とのやり取りなど、“自分で考えて動く”場面が急に増えていきます。その変化に気づかないまま、自信をなくしてしまうエンジニアは少なくありません。
本記事では、そんな「エンジニア3年目の壁」の正体と、今後のキャリアの考え方、乗り越え方をお伝えします。「このままでいいのかな?」と感じている方こそぜひ読んでみてください。
Contents
ITエンジニア3年目で「向いてない」と感じる理由
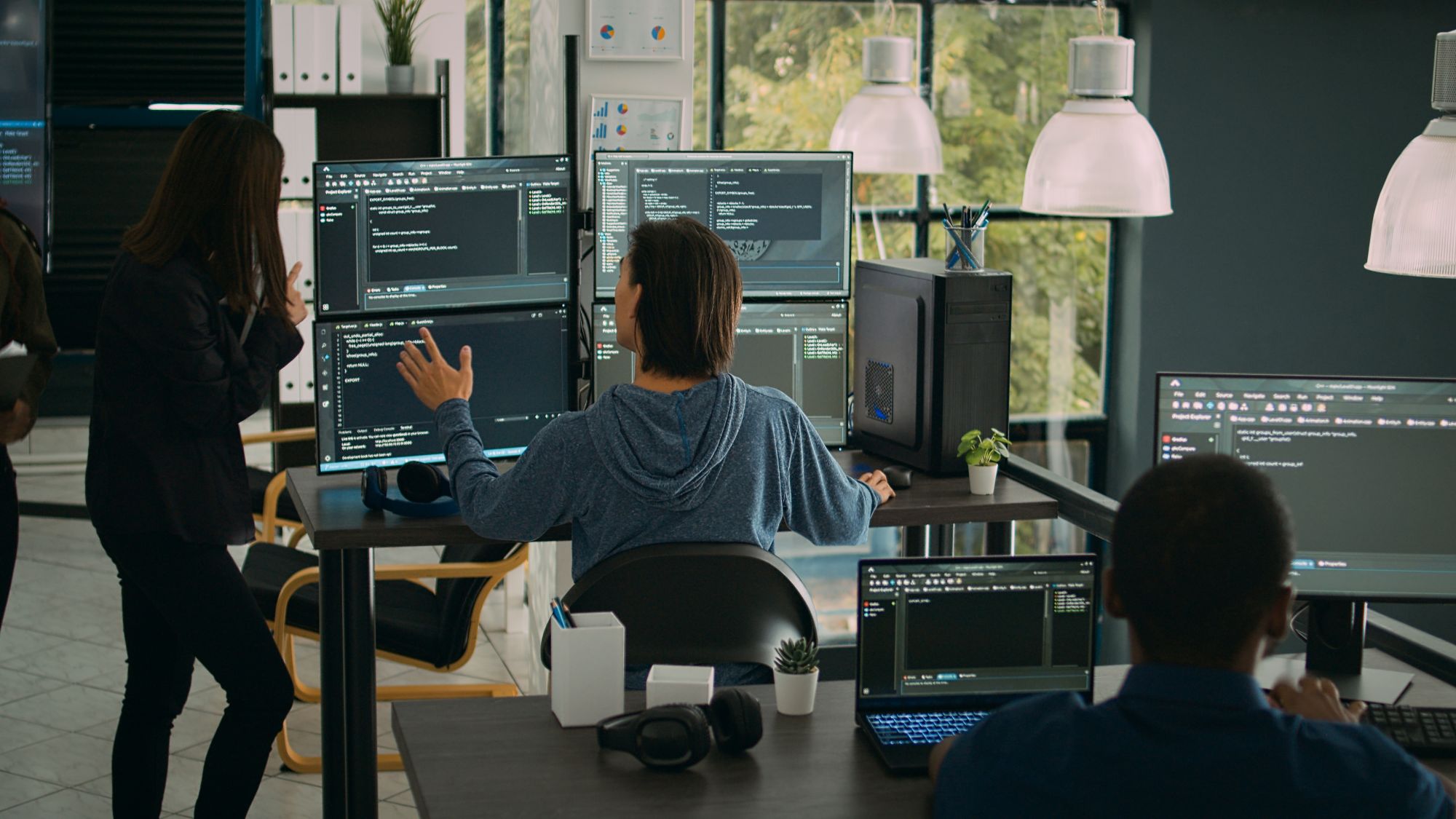
ITエンジニア3年目。そろそろ後輩もできて、現場では一人前として扱われることが増えてきた頃かもしれません。でもふとこんな気持ちになっていませんか?
「なんでこんなに作業が遅いんだろう、もしかしてエンジニア向いてない?」
「言われたとおりにしか仕事できないから、評価が低い」
「仕様の意味がわからなくて、会議でも置いてけぼり……」
実はこれ、“向いてない”わけでも“スキル不足”でもなく、仕事のフェーズが変わってきたことが原因かもしれません。ではどんな場面で“仕事できない感”が強まるのでしょうか?
1. 新しい技術・ツールに戸惑うとき
配属先が変わってこれまで使っていなかったフレームワークや言語に直面すると、一気に自信をなくしがちです。慣れれば済む話と頭ではわかっていても、手が動かず業務が遅れれば「自分が足を引っ張っているのかも」と焦ってしまいます。
2. 抽象度の高い問題解決を任されたとき
「この処理、なんでこんなに遅いのか分からない」「ログを見ても原因が特定できない」──
設計やパフォーマンス改善など、コードを書く以外の“考える仕事”が急に増えるのも3年目。経験値が追いつかず、仕事に詰まってしまうのは自然なことです。
3. リーダー的役割をふられたとき
「ちょっとこのタスク、後輩に割り振っといて」
そんな一言に「え、自分がまとめるの?」と動揺したことはありませんか?
マネージャー経験がない状態でチーム調整を任されると、「技術どうこう以前に人を動かせない」と感じて落ち込むことも。
4. 会話についていけない・伝えられないとき
クライアントや上司の会話に全くついていけず、「自分だけ空気が違う」と感じる瞬間。あるいは、「自分の言いたいことが全然伝わってない気がする」とモヤモヤすることなど。3年目以降は“黙々と書くだけ”では通用しなくなり、コミュニケーションの壁にぶつかる人も少なくありません。これらはすべて、「できない」のではなく──「求められる役割が変わった」からこその戸惑いなのです。
この見方を知るだけでも、少しは心がラクになるはずですよ。
次のセクションでは、 “3年目の壁”をどう乗り越えていくかを考えていきましょう。
ITエンジニア「3年目の壁」を乗り越えるためにできること
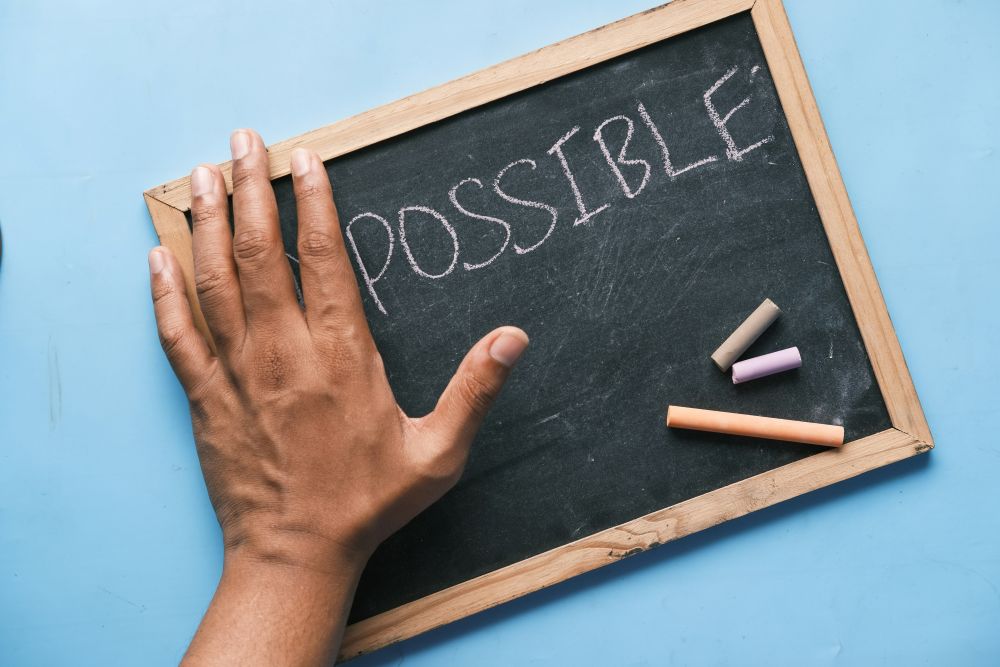
「エンジニアは離職率が高い」と思われがちですが、実際はそうではありません。
厚生労働省の雇用動向調査によれば、2023年の情報通信業の離職率は12.8%。これは、宿泊業・飲食サービス業の26.6%、医療・福祉の14.6%に比べると、むしろ低い水準です。(出典:厚生労働省 令和5年雇用動向調査結果の概況)
もちろん、「情報通信業」にはエンジニア以外(営業、事務等)も含まれるので一概には言えませんが、それでもほかの業界と比較すると差があるのがわかると思います。
また、エンジニアの場合は専門スキルが他社でも活用できるため、「離職」ではなく「キャリアアップのための転職」という側面もあります。
とはいえ、エンジニア3年目で「もう無理かも」と悩む人が多いのは事実。なぜなら、仕事の抽象度や期待される役割が急に変化し、「これまでのやり方が通用しなくなる」からです。
でも──せっかくこの道を選んだのなら、「もう少しだけ」前に進んでみませんか?
ここでは、今からできる6つの行動をご紹介します。
1. 基礎から学び直す
「ついていけない」と感じたとき、焦って新技術に手を出す前に、いま関わっているプロジェクトの“土台”を理解することが何よりも重要です。
たとえば、扱っているフレームワークのコードを追いながら「なぜこの構成になっているのか」「自分のコードがどこで呼ばれているか」といった仕組みを図解してみる。あるいは、チームのベテランが過去に書いたコードを読み込み、「実際に動いている書き方」をなぞる。
このように「現場の技術を現場で学ぶ」ことこそ、3年目の伸び悩みを打破するヒントになります。
もちろん、技術書や動画教材も補助的に役立ちます。おすすめは、実務コードを写経して解説するタイプのUdemy講座や、現場想定のアプリを作るハンズオン教材。
ポイントは、「知らないことを勉強する」よりも、「知っているはずのコードを深掘りする」ことです。
プライドを捨てて、一つひとつのコードの意味を確認しながら読み解いていくことが、最短での再成長につながります。
2. 公式ドキュメントやチュートリアルを参考にする習慣を身に付ける
3年目にもなれば、公式リファレンスの文章もある程度理解できるはず。
Stack OverflowやQiitaを検索する前に、まず一次情報にあたる習慣をつけましょう。
- APIの正確な使い方
- 想定される例外や挙動
- バージョンごとの違い
こうした知識は、現場での“思考力”を支える柱になります。
3. ツールを使って原因を“可視化”する
問題が起きたとき、感覚や経験だけで対処しようとしていませんか?デバッグツールやプロファイラを使えば、現象を客観的に観察し根本原因を突き止めやすくなります。
たとえば
- Visual Studio Codeのデバッガー、Chrome DevTools
- JavaならJProfiler、Node.jsならNode.js Profiler、New Relic など
まずは身近なツールから1つ、使いこなせるようにしてみましょう。
4. コードレビューを受ける・頼む
「どこが悪いのか自分ではわからない」──そんなときは、他人の目を借りるのが一番の近道です。上司や同僚に気軽に相談できる環境であれば理想的ですが、そうでない場合はコードレビューサービスを活用するのも有効な選択肢です。
客観的な視点から指摘を受けることで、自分では気づかなかった癖や弱点が見えてきたり、思い込んでいた“つまずきポイント”を突破しやすくなったりします。
「他人にコードを見せるのはちょっと怖い」と感じるかもしれませんが、「プロに見てもらうことでラクになる」と考えれば、ずっと前向きに取り組めるはずです。
5. マネジメントは“構造化”がカギ
3年目で初めてリーダー的ポジションに立つと、混乱するのは当然です。まずは以下の2点を明確にするだけで、グッと仕事を進めやすくなりますよ。
(1)役割と責任を明確化する
→ チーム内で「誰が何をするか」「何が終わればOKか」を共通認識に
(2)タスクに優先順位をつける
→ アイゼンハワーマトリクスで重要・緊急を整理
→ TrelloやJIRAなどのツールで可視化
全部を完璧に管理しようとせず、「まず2つ整理する」と考えるのがコツです。
6. コミュニケーションは“伝える”より“通じる”が大事
開発規模が大きくなるほど、「技術があるだけ」では評価されにくくなります。
- 上司に要点を整理して報告できるか
- 非エンジニアに技術を噛み砕いて伝えられるか
- 相手の話を最後まで聞けるか
3年目からは、こうしたビジネスコミュニケーション力が問われるフェーズに入っています。
「相手が誰か」「何を求めているか」を意識するだけで、コミュニケーションの質は大きく変わります。迷ったときは、「まず一つだけ」試してみてください。壁を越える方法は、たくさんあります。でも、全部やろうとして動けなくなるのは本末転倒。気になるものから、まず一つ──今日から始めてみませんか?
ITエンジニア3年目で転職を考えるなら|判断基準と選択肢
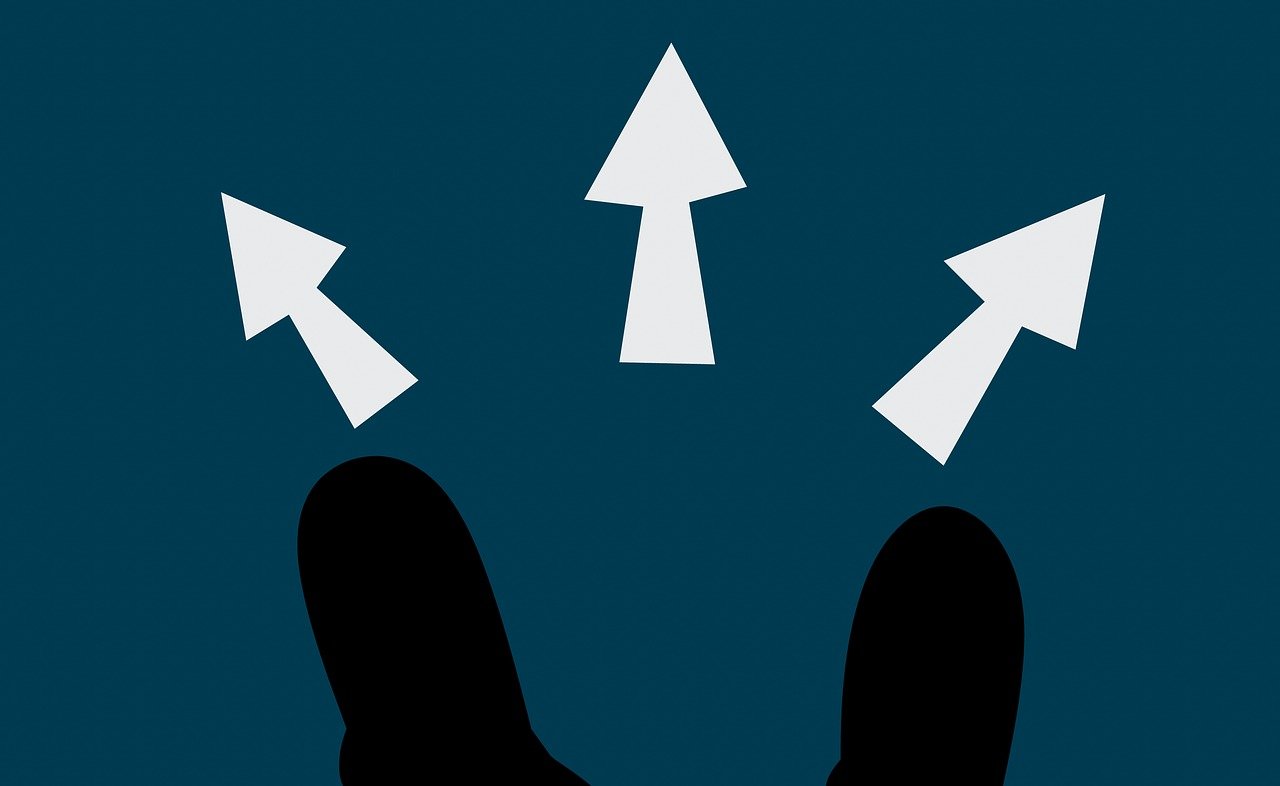
ここまでさまざまな乗り越え方をお伝えしてきましたが、それでも「頑張ってみたけれど、どうしてもつらい」「このままじゃ自分が潰れてしまいそう」──そう感じているなら、キャリアチェンジや転職を視野に入れるのも、決して間違いではありません。
エンジニア3年目というのは、まだ“若手”とされるポジションです。経験を積みながら次の一手を考えるには、まさに今が好機でもあります。
ITスキルを活かして異業種で輝く道もある
■ マーケティング職へ
データ分析やツール運用の経験があるエンジニアなら、デジタルマーケティングの現場でそのスキルが生きます。
技術を理解したマーケ担当者は、実は市場価値が非常に高い存在です。
■ コンサルティング業界へ
ITのバックグラウンドを持つ人材は、企業のDX推進や業務改善提案のプロフェッショナルとして重宝されます。「技術がわかるコンサル」は、需要の高いポジションです。
同じIT業界でも、職種を変える選択肢
■ フロントエンド → UI/UXデザイナー
「設計や見た目に興味がある」なら、技術とデザインを橋渡しするポジションもおすすめです。
■ 開発 → インフラエンジニア
バックエンドやWeb開発からステップアップして、全体設計や運用最適化を担う立場へ進む道も。クラウド技術に強みがあれば、さらに市場価値は高まりますよ。
■ エンジニア → プリセールス
顧客対応や製品提案に関心があるなら、技術と営業の中間に立つ役割も選択肢です。提案書作成・デモ・Q&A対応など、社内外から頼られる存在になれるでしょう。
「今の環境がすべてじゃない」と知ることが第一歩
技術職は、職場やポジションとの相性を考慮することが非常に大切な職種です。
もし今の現場で「評価されない」「向いていない」と感じても、それは環境が合っていないだけかもしれません。あなたが本来の力を発揮できる場所は、きっとあります。
▼あわせて読みたい▼
20代女性エンジニアのリアルな悩みとキャリアの考え方
「エンジニア3年目、向いていないかも」と感じやすいのは、責任や期待が一気に高まる時期だからです。同じように悩みながらキャリアを考えている20代エンジニアの事例も、次の一歩を考えるヒントになります。
よくある悩みQ&A|3年目ITエンジニアのリアルな声

Q1.エンジニア3年目で求められる「レベル」や「スキル」はなんですか?
A1.言われたことをこなすフェーズから、3年目では「自分で考えて動く」フェーズへと変化します 。要件整理や設計、パフォーマンス改善、後輩の指導といった、より抽象度の高い問題解決能力やマネジメント能力が求められるようになることが多いです。
Q2: 3年目のエンジニアは、新しく資格を取ったほうがいいですか?
A2. AWSやGCP等のクラウド技術、PMPなどのプロジェクトマネジメント系の資格は市場価値を高める上で有効でしょう。前提として、資格取得よりもまずは現在のプロジェクトの基盤技術を深く理解し、現場で活かせるスキルを身につけることが重要です 。
Q3.3年目に入ったけど、目標を見失いつつあります。
A3.ビジネスコミュニケーション力の向上や、チーム全体の生産性を高めるためのマネジメント能力を目標にすることをおすすめします 。「要点を整理して上司に報告する」「非エンジニアに技術を分かりやすく説明する」等を日々の業務で実践していくのはいかがでしょうか。
まとめ|「エンジニアに向いてない」と決めつけないことが大事

ITエンジニア3年目は仕事の難易度が上がり、求められる役割も変わってくる“転機”の時期といえます。「仕事ができない」と感じるのは、実はあなた自身が成長フェーズに差しかかっている証かもしれません。理想と現実のギャップに悩んだり、ふと自信をなくしたりするのは、誰にでも起こりうること。
でも「何が原因なのか?」を丁寧に見つめ直し、ひとつずつ解決に向けて動いていけば状況は変えられますし、その過程そのものがスキルアップにつながることも多いのです。技術も環境も、成長のためのサポートも、今はたくさん揃っています。
独りで抱え込まずに、ツールや人の力も借りながら、“自分なりのペース”で歩んでいきましょう。
それでも、「どうしても合わない」「今の場所では前に進めない」──そんなときは、キャリアの軸そのものを見直す時期かもしれません。
エンジニアとしての経験は、どんな分野でも価値あるスキルです。思いきって環境を変えることで、本来の自分を活かせる働き方が見えてくることもあります。
関連記事はこちら↓
当社では、技術に自信がないと悩むITエンジニアの方にも寄り添い、
キャリアに合った現場との出会いをサポートしています。
「自分に合った働き方を知りたい」「現場を変えたいけど、不安がある」
そんなときは、ぜひ一度ご相談ください。



