フロントエンドエンジニアがつらいと感じる理由|生成AI時代に増えた「判断のしんどさ」とは
2023/09/22
SESと派遣の違いを徹底解説!あなたはSESの雇用形態に向いているかチェック

Last Updated on 2025年10月9日 by idh-recruit
「SESって常駐?それとも派遣?」
ITエンジニアとして就職・転職活動をしていると、よく目にするこの働き方。だけど、実際の雇用形態や契約の仕組みは意外とわかりにくく、「派遣っぽいけど正社員?」「安定してるの?」とモヤモヤする方も多いのではないでしょうか。
実際、SESという働き方には“常駐型”の側面がありつつ、法律的には派遣と異なる独自の仕組みがあります。客先常駐歴の長いベテランエンジニアであれば、このようなエンジニア派遣の仕組みついてはすでにご存じでしょう。
本記事では、主にSESエンジニアとして働くことを検討している方に向けて、SESの雇用形態や働き方の実態をわかりやすく整理しました。派遣との違いや安定して働ける企業の見極め方まで詳しく解説。「SESに興味はあるけれど、仕組みが曖昧でちょっと不安……」という方は、ぜひ最後までご覧ください。
Contents
SESって常駐?エンジニア派遣の雇用形態を整理しよう
「SESって常駐って聞くけど、それって派遣とどう違うの?」
そんな疑問を持ったことはありませんか?
IT業界では「常駐」「派遣」「SES」といった言葉が飛び交い、混同されがちですが、実はそれぞれ契約形態や働き方の中身が大きく異なります。
まずは、こうした働き方の土台となる「エンジニア派遣」の基本から整理しておきましょう。
派遣とは、労働者が派遣会社(派遣元)と雇用契約を結び、その会社から紹介されたクライアント企業(派遣先)で働く仕組みです。 給与は派遣会社から支払われますが、実際の勤務先は派遣先企業となります。
この仕組みをふまえると、エンジニア派遣とは「派遣会社に所属するエンジニアが、派遣先企業で開発業務などを行う働き方」のこと。世間ではこのような形態をひとまとめに「エンジニア派遣」と呼ぶことが多いのですが、SESと派遣は実際や異なるルールや仕組みのもとで成り立っています。
雇用形態や指揮命令系統、安定性の面でも違いがあるので、このあと詳しく「登録型派遣」と「常用型派遣(=SES)」の違いや、SESの雇用実態、そして“常駐”という働き方の本質を解説していきます。
ちなみに、業界では「常用型派遣」を「正社員型派遣」と呼ぶケースもあります。
派遣会社の正社員として雇用され、安定した収入を得ながらクライアント先で働くスタイルを指す点で、常用型派遣と同義です。
↓あわせて読みたい↓
エンジニア派遣の仕組み
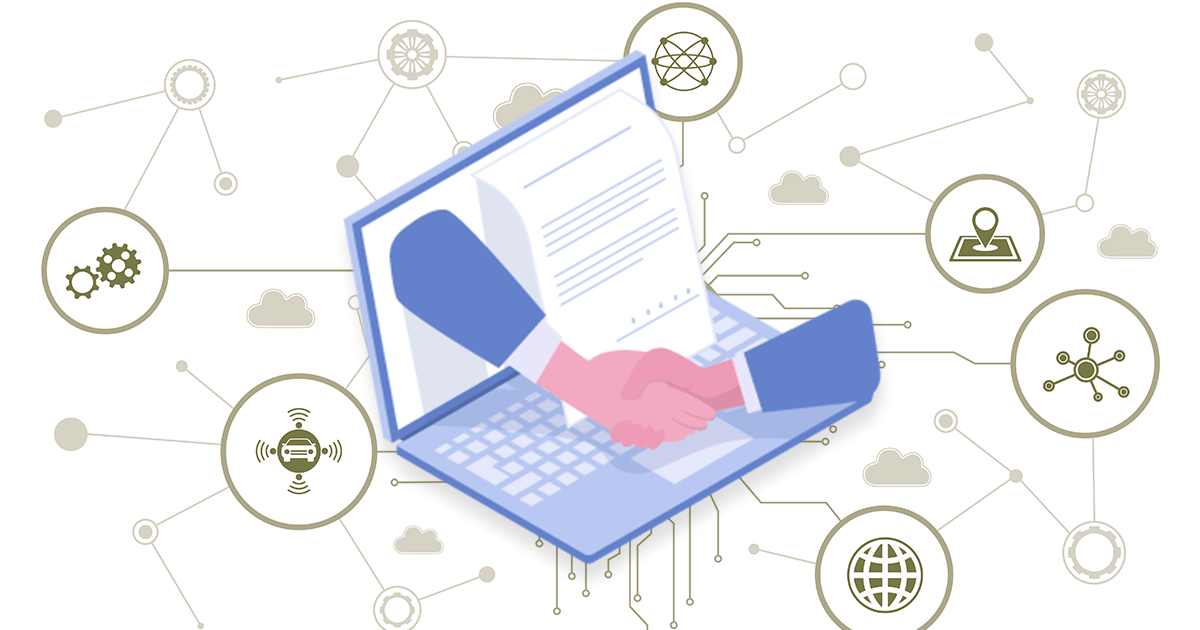
次に、エンジニア派遣がどのように成り立っているのか、その仕組みと背景を見ていきましょう。
エンジニア派遣が必要になるのはなぜ?
企業がWebサービスやシステムを開発するには、専門的なスキルや実務経験を持つエンジニアが必要です。 しかし、そうした人材を常に自社だけでまかなうのは難しいのが現実。
新人をイチから育成するには時間とコストがかかりますし、経験豊富なエンジニアを正社員として雇い続けるのも負担が大きい。
けれど、開発プロジェクトは止められない──。
そんなとき、“助っ人”のような形で活用されるのが、エンジニア派遣のサービスなのです。
エンジニア派遣の仕組み・ビジネスモデル
クライアント企業が「開発に必要なエンジニアが足りない」と派遣会社に依頼すると、 派遣会社はその要望に合う人材を自社の登録エンジニアから選び、クライアントに派遣します。
流れとしては以下のようになります:
– クライアント企業 → 派遣会社に依頼
– 派遣会社 → エンジニアを選定・派遣
– エンジニア → クライアント先で業務を担当
– クライアント企業 → 派遣会社に派遣料を支払う
– 派遣会社 → エンジニアに給与を支払う
このサイクルが、エンジニア派遣の基本的なビジネスモデルです。
雇用形態の違いを比較!登録型派遣と常用型派遣(SES)
エンジニア派遣は主に次の2種類の雇用形態に大別され、同じ派遣として働くエンジニアでもその内容(働き方)は大きく異なります。
●登録型派遣
「派遣会社の派遣スタッフ」と聞いて多くの方が思い浮かべるのが、この登録型派遣。 登録型派遣はエンジニアが派遣会社に登録し、派遣会社と期間を定めて雇用契約を結ぶ雇用形態のこと。つまり、雇用期間はエンジニアがクライアント企業に派遣されている期間(有期雇用)に限られます。そのため、派遣されていない期間は派遣会社からの給与が発生しません。 また、派遣スタッフに業務上の具体的な指示を与えるのは、実際に働くクライアント企業(派遣先)です。
●常用型派遣(SES)
常用型派遣は、派遣会社と期間を定めずに雇用契約を結ぶ雇用形態です。 無期雇用となるため、特段の問題がなければ派遣会社が定める定年まで勤められます。 常用型派遣の場合、雇用主はあくまで派遣会社です。エンジニアとクライアント企業との関係は準委任契約であることが多く、業務上の具体的な指示は雇用主である派遣会社から与えられる点が特徴です。 そして、クライアント企業へ派遣されていない期間(待機期間)も、派遣会社からの給与が発生します。
この常用型派遣でエンジニアを無期雇用し、クライアント企業に人材を提供している代表的な企業形態がSES(システムエンジニアリングサービス)です。SES企業は所属エンジニアを正社員として雇用していることがほとんど。
以上のことから、求人票をチェックする際、客先常駐としながらも雇用形態が「正社員」となっている場合は、常用型派遣のSES企業であると見て間違いないでしょう。 前述した「クライアント先に出向いて働く派遣エンジニアであるにもかかわらず、実体は派遣会社の正社員」というケースは、多くの場合、このSES企業から派遣されたエンジニアのことを指すのです。
▼「働きやすい!」「今までで一番ホワイト」満足の声が多数届くSES企業アイ・ディ・エイチ
登録型派遣と常用型派遣、それぞれのメリット・デメリットを徹底解説
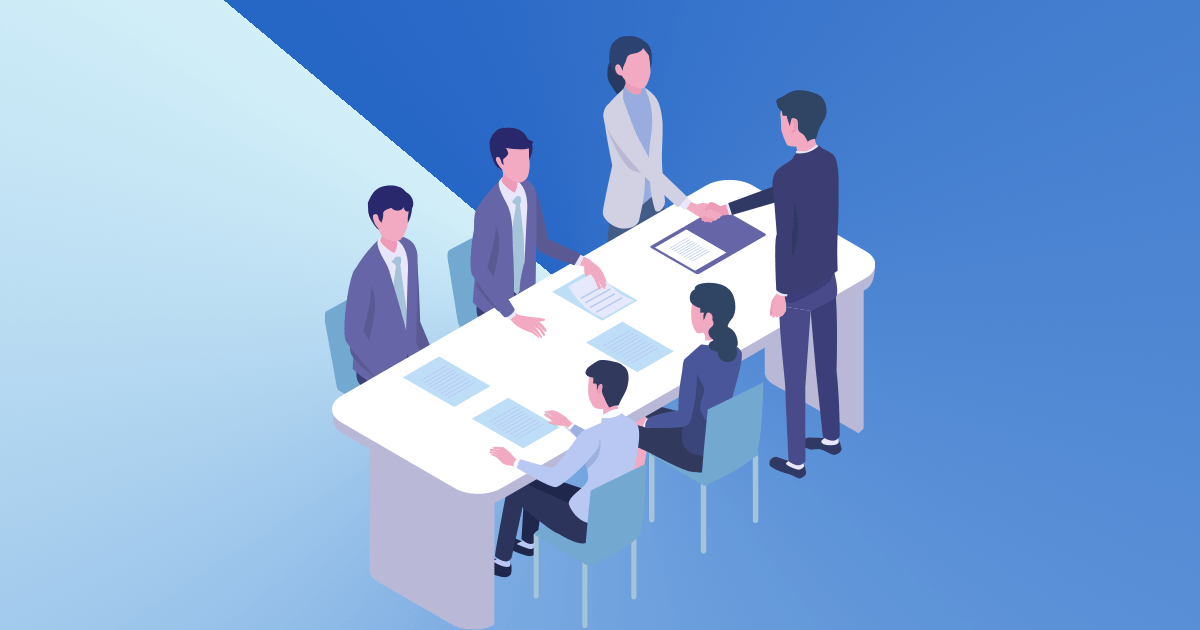
上で紹介した登録型派遣と常用型派遣の仕組みには、それぞれに意外なメリット・デメリットもあります。
登録型派遣のメリット・デメリット
<メリット>
・ライフスタイルやライフステージに合わせて自由に働ける
登録型派遣で募集されている仕事は、契約期間が比較的短期であったり、勤務時間を選べたりするものが多く、「数ヶ月だけ働きたい」「育児と両立させるため時短勤務したい」といった希望が叶いやすい傾向があります。 結婚や出産・育児、介護をはじめ、移住や副業なども含めたライフステージ・ライフスタイルに合わせて仕事を選ぶ自由がある点は、登録型派遣の大きなメリットです。
・さまざまな職場を経験できる
前述の通り、登録型派遣の仕事は契約期間が短いものが多く、さらに登録型派遣のスタッフが同じ職場で働けるのは最長3年です。つまり、長期の仕事であっても3年で職場を変えられるため、一つの場所にとらわれず、さまざまな職場で経験を積みたい方にとってはメリットです。
<デメリット>
・責任ある業務を任されにくい
クライアント企業の正社員に比べ優先度が低いうえ、派遣期間に上限があるため、責任ある業務を任されにくい点はデメリットです。キャリアアップを目指したい方は、ある程度スキルが身についた後に正社員へのステップアップを検討することをおすすめします。
・働く環境がリセットされる
原則、派遣期間には3年の上限があるため、その都度働く環境がリセットされてしまいます。さまざまな職場を経験したい方にとってはメリットとなりますが、腰を据えて働きたい方にとっては、職場が変わる度に新たな人間関係や職場環境に慣れる必要があるため、ストレスが溜まりやすく、デメリットの側面が強くなります。
・収入が安定しにくい
不況やクライアント企業の業績悪化、事業再編などの理由でクライアント企業から派遣会社への依頼がなくなった場合(いわゆる派遣切り)、「仕事がある間だけの雇用」が前提となっている登録型派遣では収入が途絶え、安定しません。
常用型派遣(SES)のメリット・デメリット
<メリット>
・雇用と収入が安定する
常用型派遣は派遣会社を雇用主とする無期雇用であり(多くの場合、正社員雇用)、クライアント企業から人材提供依頼がなくなった場合でも派遣会社に雇用され続け、待機期間中も給与が発生します。(待機期間中の給与額は所属する派遣会社によって異なります) 雇用と収入の安定は常用型派遣の大きなメリットと言ってよいでしょう。
・長期にわたり同じ職場で働いてスキルアップできる
登録型派遣の場合、同じ職場での勤務は最長3年ですが、常用型派遣の場合はこのような期間の制限がありません。そのため、同じ職場で長期間働いて着実にスキルアップできます。
・派遣会社によってはボーナスや各種手当が支給されることも
エンジニアを自社の社員として雇用する常用型派遣の場合は、通常の会社員と同じようにボーナスが支給されることがありますし、派遣会社内でマネジメントを担当する役職に就いたり資格を取得したりすれば、それぞれに見合った手当を受け取れることもあります。
<デメリット>
・派遣会社によっては派遣先を選べないことがある
常用型雇用において指揮命令権を持つのは派遣会社であるため、場合によってはエンジニアがクライアント企業(案件)を選べず、自身のスキルや希望する条件に合わない仕事に従事しなければならないことがあります。 ※なお、当社ではエンジニアの意思と意欲を最大限に尊重するため、案件の自由選択制を採用。会社都合の強引なアサインはありません。
・スキルや経験によっては想定より給与が低くなることがある
エンジニアは高いスキルが求められる技術職なので、ほかの職種より給与水準が高くなる傾向にあります。しかし、スキルや経験が乏しい間は単価の低い案件にしかアサインされないことも。
給与・待遇・キャリアパスの違い
ここまで、登録型派遣と常用型派遣それぞれの特徴やメリット・デメリットを見てきました。
では、実際に働くうえで気になる「給与・待遇・キャリアパス」には、どのような違いがあるのでしょうか。
給与面
まず給与面では、常用型派遣の方が比較的安定しやすい傾向にあります。 派遣会社に正社員として雇用されているため、待機期間中でも給与が支払われる場合が多く、長期的な収入の見通しが立てやすいのが特徴です。 一方、登録型派遣は「仕事があるときだけ雇用される」スタイルのため、案件が終了したりいわゆる“派遣切り”に遭ったりすると、収入が一時的にゼロになるリスクがあります。
待遇面
常用型派遣ではボーナスや各種手当、社会保険などが整備されているケースが多く、福利厚生の面では一般的な正社員に近い待遇を受けられることも。登録型派遣ではこうした制度は最小限に留まる場合が多く、短期就業が前提のためキャリアアップ支援や教育体制が薄い傾向があります。
キャリアパス
登録型派遣ではさまざまな職場を経験できる反面、業務の責任範囲が限定されやすく、スキルの深掘りや昇進・役職登用といった道筋は描きづらい側面があります。
対して常用型派遣では、同じ職場で長期的に働いたり、派遣会社内でポジションを得たりと、社内キャリアや専門性を高める方向に進みやすい環境が用意されているケースもあります。
このように、雇用の安定性や待遇、キャリアの築き方などにおいて、登録型派遣と常用型派遣は大きく異なります。 どちらが自分に合っているかは、「柔軟性を重視したいのか」「安定と成長を重視したいのか」といった価値観によっても変わってくるといえます。
あなたはどっち?SESに向いている人・向いていない人
SESに向いている人の特徴
生活の安定を重視したい人
SESでは、派遣会社の正社員として無期雇用されるケースが多く、給与や社会保険などが安定しています。 フリーランスや登録型派遣での働き方に不安を感じている方や、結婚・出産・子育てなどライフイベントを控えている方にとっては、SESのような働き方が安心材料になることも多いでしょう。
じっくりスキルを磨きたい人
SESでは、同じ現場で比較的長期的に働けるケースが多く、業務に継続的に関わる中で着実にスキルを深めていくことができます。
「短期ではなく、中長期で一つの分野に集中したい」という方には、SESのような常用型の働き方がマッチします。
将来的にマネジメントにも関わりたい人
SESでは、案件によってはPM(プロジェクトマネージャー)やPL(プロジェクトリーダー)といったマネジメント職を任されることもあります。 登録型派遣に比べると、長期的な配属や社内昇格の機会があるぶん、キャリアの幅も広げやすい環境といえるでしょう。
SESに向いていない人の特徴
働く時間や場所をもっと柔軟に選びたい人
勤務地や勤務時間、契約期間にこだわりたい場合は、案件ごとに働ける登録型派遣やフリーランスの方が向いているかもしれません。 SESでは長期配属が前提となることも多く、自由な働き方を求める人には窮屈に感じることもあります。
多様な現場を経験したい人
「短期サイクルでいろいろな会社を渡り歩きたい」「社風や業種を変えながら幅広い経験を積みたい」という方にとっては、3年で職場が変わる登録型派遣の方が適しているでしょう。 SESは基本的に長期的な配属が多いため、変化を楽しみたいタイプには物足りなさを感じることも。
自分で案件を選びたい人
SESでは、案件アサインの決定権は基本的に派遣会社側にあります。 企業によってはエンジニアの希望を考慮してくれるケースもありますが、すべての案件を自由に選べるわけではありません。
「仕事内容や働く場所は自分で決めたい」というスタンスが強い方には、登録型派遣やフリーランスなどの働き方がより合っているかもしれません。
このように、SESが合うかどうかは、安定志向・キャリア志向・自由度へのニーズによって大きく分かれます。
「自分はどんな働き方をしたいのか?」を考えるきっかけにしてみてください。
【FAQ】SESに関するよくある質問
Q1.SESって不安定とかブラックってよく言われてますが、実際そうなんですか?
確かに、業界全体では「現場を転々とさせられる」「フォローがない」などの理由から、不安定・ブラックと感じる人がいたのも事実です。 ただし、それはあくまで“会社による”というのが実際のところ。 正社員雇用で安定した収入やサポート体制を整えているSES企業も増えており、職場環境や成長支援に力を入れている企業を選べば、安心して働けます。
Q2.SESはキャリアにならないって本当ですか?
決してそんなことはありません。 たしかに、単純な作業しか任されないような環境ではスキルアップにつながりにくいこともありますが、これはSESに限らずどんな職場でも同じことが言えます。 むしろ、幅広い業界・技術領域に触れられるのはSESの強みでもあり、意欲次第で十分キャリアを築いていけます。 実際にSESからスタートして、PMやCTOなどにステップアップしているエンジニアもたくさんいます。
Q3.常駐先の現場って自分で選べますか?
会社や契約形態によって異なりますが、多くのSES企業では希望やスキルに合った案件をすり合わせた上でアサインされます。 「選べない」ではなく、「相談しながら一緒に決めていく」というケースが多いため、希望の業界や働き方、身につけたい技術などがあれば面談時にしっかり共有しておくのがポイントです。
Q4.SES常駐先の現場が自分に合わなかったどうしたらいい?
合わないと感じた場合は、まずは配属企業の担当者や営業に相談するのが一般的です。 すぐに交代できるかどうかは案件の契約条件によりますが、無理に長期間続けさせられることはありません。 定期的な面談やサポート体制がある企業なら、早期に軌道修正できる環境が整っていることが多いです。
まとめ|常駐SESはじっくりスキルを磨ける選択肢
「SESって常駐?それとも派遣?」──本記事では、そんな疑問を抱く方に向けて、SESの雇用形態や派遣との違い、そして働き方の実態について詳しく解説してきました。
同じ「エンジニア派遣」と呼ばれる働き方でも、登録型派遣・常用型派遣・SESでは、契約形態も、安定性も、キャリアの築き方も大きく異なります。
中でもSESは、「正社員としての安定」と「多様な現場での経験」のバランスを取りながら、長期的に常駐し、じっくりスキルを磨ける選択肢のひとつ。 もちろん、会社選びによって環境は大きく変わるため、自分に合った職場を見極めることが何より重要です。
▼アイ・ディ・エイチでは、エンジニア一人ひとりの希望や成長を大切にしています。
案件の強制アサインや帰社日など、従来のSESで感じがちなストレスとは無縁の環境で、スキルアップと安定した働き方の両立を目指しませんか?
ご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にエントリーください。



