フロントエンドエンジニアがつらいと感じる理由|生成AI時代に増えた「判断のしんどさ」とは
2023/11/10
エンジニアの激務は回避できる! 10の原因と現状を変える4つのアクション
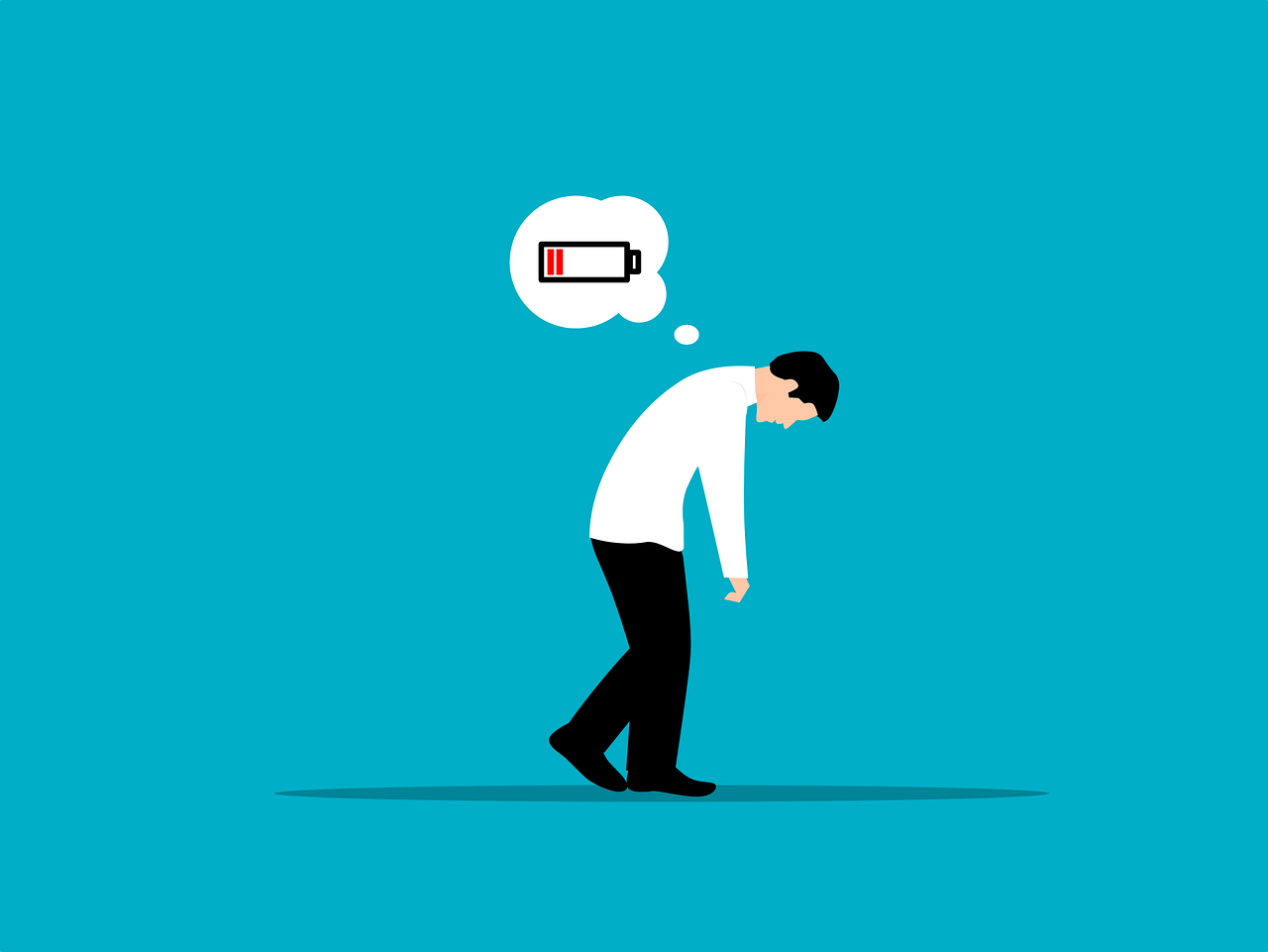
Last Updated on 2025年9月2日 by idh-recruit
「毎日終電近くまで残業」
「休日にも障害対応の電話が鳴る」
「新しい技術を学びたいのに、時間がない」
こんな日々を送っているエンジニアの方、多いのではないでしょうか?
エンジニアという仕事にやりがいを感じているものの、現実の働き方は想像以上にハード。技術への情熱はあるのに、過酷な労働環境に心身ともに疲弊してしまう──そんな状況に陥っているエンジニアは少なくありません。
そこで今回は、エンジニアが激務だと言われている理由と、過酷な労働を回避する方法について詳しく解説します。今の働き方に疑問を感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。
【この記事を書いた人】
<hide>
大学で情報系工学を専攻し、卒業後はIT業界一筋。10年以上のキャリアを積んできたエンジニアです。
様々な経験と幅広いスキルを追求できる「案件自由選択制SES」という働き方と、「お客様とHappy-Happyの関係を築く」という理念に共感し、IDHに転職しました。
Web系エンジニアとして、Java、Ruby、Pythonなどを中心に、フロントエンドからサーバーサイドまで、設計・プログラミング・テストと一貫して担当。これまでに通信インフラ、広告配信、人材派遣、金融、ECサービス、IoTなど多岐にわたるプロジェクトに携わりました。
Contents
エンジニアが激務だと言われる10の理由
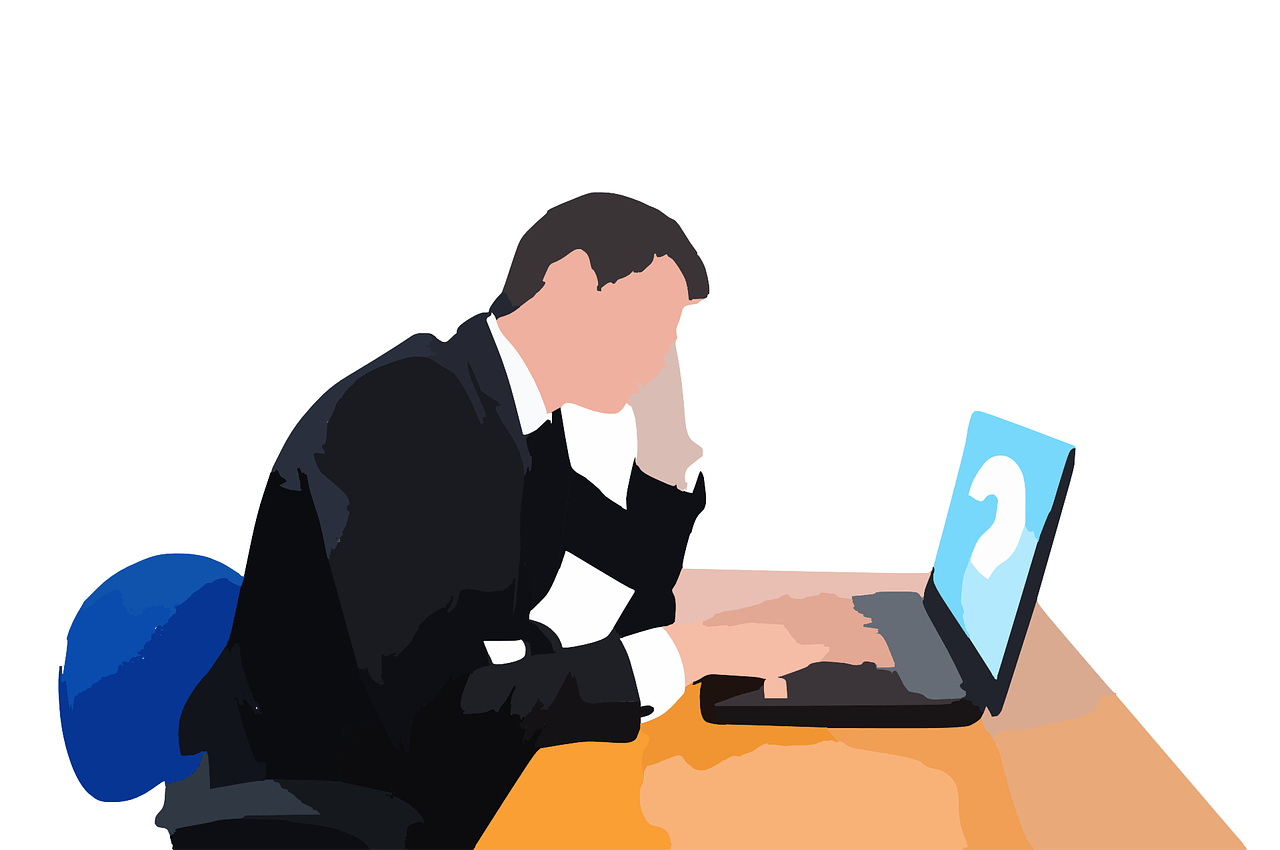
【1】IT技術は日進月歩。「一生勉強」のプレッシャー
「エンジニアは一生勉強し続けなければならない」という話を聞いたことがあると思います。常に進化を続けるIT業界では、新しいプログラミング言語が次々と登場し、システムのアップデートは日常茶飯事。「半年前の技術トレンドがもう古い」なんていうこともあるため、スキルや知識の継続的な更新は欠かせません。
また、Web、金融、医療など、多岐にわたる業界のシステム開発に携わる機会も多く、その都度、異なる専門知識や業務フローを覚える必要があります。
「エンジニアは覚えることが多すぎる……」──そんな溜息が聞こえてきそうなほどのインプット量と、終わりなく続く学習に向き合う現実が、激務につながるプレッシャーとなるのです。
【2】「もっと良くできるはず」終わりの見えない品質追求
エンジニアの仕事は、「これ以上やることはない」という明確なゴールが見えにくい性質を持っています。
例えば設計段階では、設計漏れによる後工程での手戻りや納期の遅れを防ぐために、第三者によるレビューを行います。レビューで改善点や問題点を指摘されることがなかったとしても、心配性の人は「何か見落としがあるのでは?」と必要以上に何度も見直してしまうのです。また、実装が完了した後も「このコードはもっときれいにできる」「この設計はもっとシンプルになる」と、自主的に改善を続けてしまうことも少なくありません。
つまり、プロ意識が高い人ほど「もっと良くできるはず」と考えてしまい、作業に終わりが見えなくなるのです。品質を追求する気持ちは重要ですが、こうした完璧主義が、結果的に長時間労働につながる原因となります。
【3】リモートワークの落とし穴。オン・オフの切り替えができない!
ITエンジニアの仕事はパソコン一つで完結することが多いため、リモートワークとの相性が非常に良いとされています。実際に、コロナ禍後でもフルリモートの案件は多数あり、通勤の負担がないなどの働きやすさを感じている人も多いでしょう。
しかし、そこに落とし穴があります。自宅に仕事用のパソコンが常にある環境では、仕事とプライベートの境界線が曖昧になりがちです。「ちょっと気になることがあって」と退勤後や休日にPCの電源を入れてしまい、それをきっかけに業務時間外の作業をしてしまうことも少なくありません。物理的にオフィスを離れることで仕事と区切りをつけていた人ほど、このオン・オフの切り替えができない現実に悩まされることになります。
【4】「間に合わない!」納期に追われる切迫感
開発のゴールの一つは、お客様から要望された製品を納期までに納品することです。案件によっては、不測の事態が起きても納期を調整できる場合がありますが、新サービスのリリース日がメディアで公表されている場合や、法律改正に伴うシステム改修では、納期を動かすことができません。
こうした絶対的な納期がある中で、開発中に想定外のトラブルや遅延が発生すると、残された時間はどんどん削られていきます。すると、「このままでは間に合わない!」という切迫感と戦いながら、納期を厳守するために残業や休日出勤を余儀なくされてしまいます。何が何でも間に合わせなければならないという重圧が、エンジニアを心身ともに激務へと追い込んでいくのです。
【5】「ルーティンワークだけやりたい」そんな人には不向き
毎日同じ作業の繰り返しではないのが、エンジニアの仕事です。お客様の要望は常に異なるため、全く同じ作業というのはほとんどなく、設計や実装などの各工程では、その都度、最適な解決策を見つける必要があります。
また、予期せぬトラブルや障害が発生した際には、その日の作業内容がガラリと変わってしまうことも珍しくありません。このような予測不能な出来事にも柔軟に対応しなければならないため、常に新しい情報をインプットし、思考し、判断し続ける必要があります。「決まった作業を淡々とこなしたい」と考える人には、この予測不能な日々が激務と感じられる原因となります。
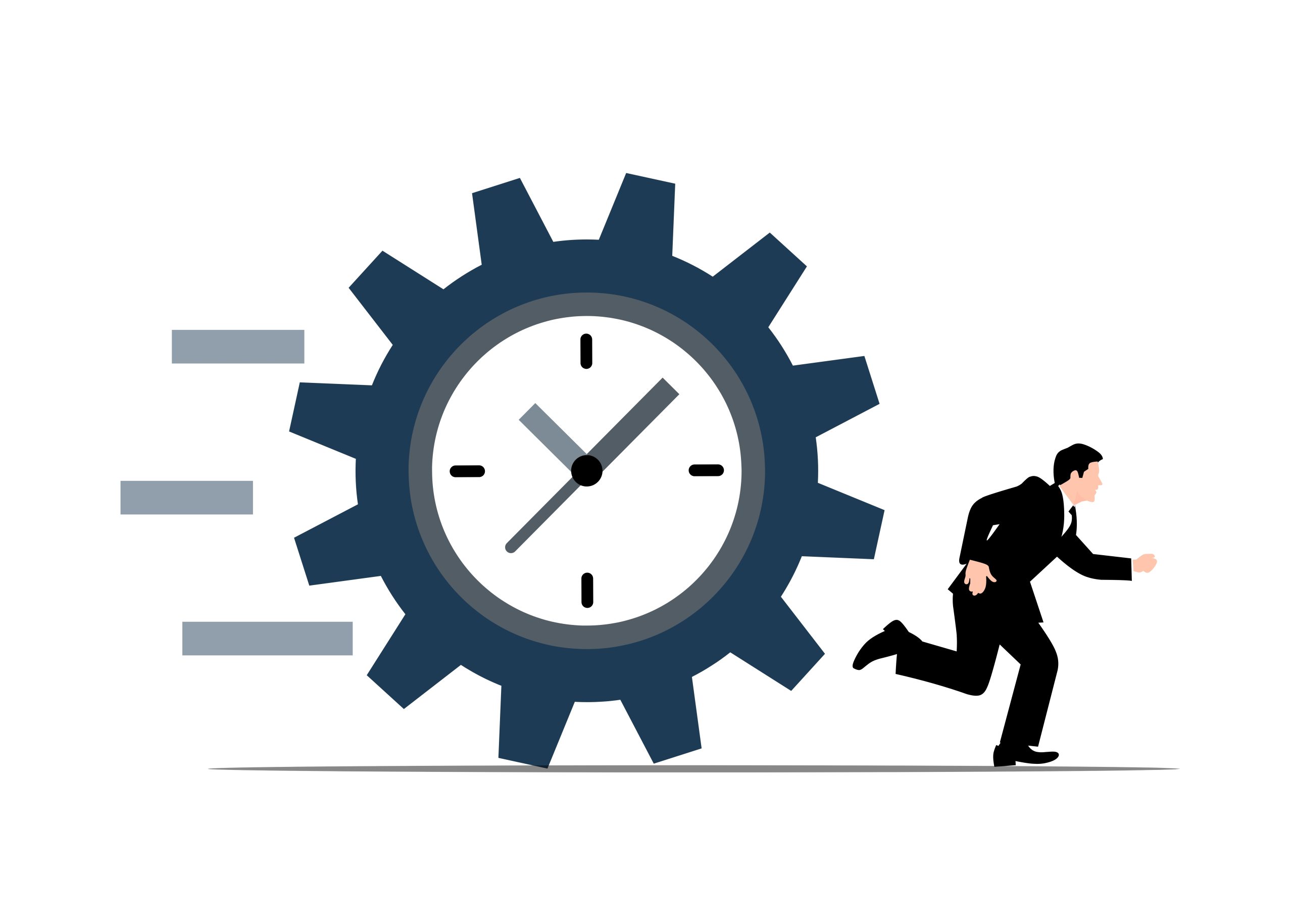
【6】「またやり直し?」予期せぬ仕様変更に振り回される日々
エンジニアの仕事は、PM(プロジェクトマネージャー)が管理するスケジュールに沿って進むのが一般的です。しかし、初期の要件定義や設計に考慮漏れがあると、急な仕様変更が必要になることがあります。特に、設計工程が終わった後の製造やテスト工程で仕様変更が発覚すると、影響範囲が大きく、設計以降の工程が全てやり直しになってしまうこともしばしば…。さらに、納期間近にお客様から急な要望が入ることもあり、開発当初のスケジュールにはなかった変更への迅速な対応が求められる場面も少なくありません。
こうした手戻りの作業に振り回される日々が続くと、エンジニアは「またやり直し……」と、心身ともに疲弊してしまうのです。
【7】想定外のトラブル。いつ起こるかわからない障害対応
サービスが稼働した後、いつ起こるか予測できない不具合や想定外の障害は、エンジニアに大きな負担をかけます。例えば、Webアプリケーションでバグが発生した場合は早急に改修が必要ですし、アクセスが急増してサービスが停止すれば、夜間でも休日でも復旧作業に追われることになります。さらに、不正アクセスが起これば、情報漏洩を防ぐために一刻を争うセキュリティ対策が求められます。
特に24時間365日稼働しているシステムでは、夜間や休日でも障害対応の電話が鳴り響くことがあります。こうした突発的かつ緊急性の高い対応に追われると、「プライベートの時間も気が休まらない」という状況に陥ってしまいがち。予測不能なトラブル対応の多さも、エンジニアが激務になる大きな理由の一つです。
【8】経験とともに増す「見えない業務」で気力が消耗
エンジニアは、プログラミングだけをしていれば良いわけではありません。経験の浅いプログラマーであってもチームメンバーとのコミュニケーションは不可欠ですし、さらに経験を重ねるにつれてプログラミング以外の仕事が増え、それが苦痛になり激務と感じることもあります。
例えば、SE(システムエンジニア)になると設計書の作成やテストなど担当範囲が拡大し、PL(プロジェクトリーダー)やPM(プロジェクトマネージャー)といった責任ある立場であれば、会議やメンバーのフォロー、管理業務が時間の多くを占めるようになります。こうしたプログラミング以外の「見えない業務」が増えることで、本来やりたかった開発業務とのギャップに苦しむようになり、結果的に気力を消耗させてしまうのです。
【9】デスマーチ確定!?炎上プロジェクトへの投入
プロジェクトのリリース直前の仕様変更や、深刻な不具合に見舞われるなど、いわゆる「炎上プロジェクト」と呼ばれる案件があります。こうした火の海の現場に配属されたエンジニアは、文字通り火消し役として、時間的余裕のない中で問題解決に奔走することになります。
IT業界は人手不足が深刻なため、経験の浅いエンジニアが容赦なく炎上プロジェクトに投入されることも珍しくありません。未経験ながらも長時間にわたるテストや山積みのバグ修正に追われ、他のメンバーも多忙なため、相談すらままならない孤立無援な環境に置かれてしまいます。このような状況は、心身に極度の疲弊と大きなプレッシャーをもたらし、「デスマーチ」と呼ばれる過酷な労働状態を招いてしまうのです。
【10】人間関係も業務もリセット!SESの現場変更による心労
SESエンジニアは、契約に基づいてお客様先の現場に配属となり、業務を行います。しかし、お客様から契約延長の依頼がなければ、その現場での業務は終了。その後は都度、新しい現場の採用面談を経て、次の職場へと異動することになります。
この「現場変更」が、大きな心労の原因です。新しい現場では、業務内容や開発ルールをゼロから覚え直す必要があり、同時にチームメンバーも一新されるため、人間関係や信頼関係も一から築き直さなければなりません。せっかく慣れた頃にまたリセットされ、次の現場へ──。このサイクルが繰り返されると、常に新しい環境への適応を強いられることになり、精神的に安定しづらくなってしまいます。
激務を避けて自分に合った働き方を見つけたい方は、IDHの採用ページもぜひご覧ください。
エンジニアが激務を回避する方法とは?


「やはりエンジニアは激務から逃れられないのか……」そう諦めている方もいるかもしれません。 確かに、これまでご紹介したようにエンジニアにとっての厳しい現実はあります。しかし、すべてのエンジニアが等しく疲弊しているわけではありません。
実は、激務を根本的に回避し、自分らしく働くための方法があるのです。今まさに「疲労もストレスも限界だ」と感じている方こそ、次の章でご紹介する具体的な方法をぜひ検討してみてください。
【1】まずは業務を効率化してみる
激務の原因が自身の業務への取り組み方にあると感じているなら、まずは「業務の効率化」から始めてみましょう。例えば、要件に問題があることを早い段階で発見し、お客様に提示できれば、後工程での大きな手戻りを防ぐことができます。また、タスクをチェックシートやTo Doリストで可視化し、作業完了の定義を明確にすることも効果的です。さらに、手動で行っている作業を自動化することで、作業時間を大幅に削減できるかもしれません。もちろん、スキル不足が長時間労働につながっている場合は、不足している知識を補うための勉強も重要です。
このように業務の進め方を工夫し、自分でできる改善から取り組むことで、今の環境でも激務を解消できる可能性があります。
【2】向き不向きを知るために、職種を変えてみる
SESエンジニアの場合、常駐先の変更は今持っているスキルを活かすことが前提となります。しかし、激務を回避する解決策として、職種自体を変えてみるのも有効な手段です。
一例として、Webエンジニアからインフラエンジニアへ、あるいはその逆の職種変更などは、IT業界ではよくある話です。同じエンジニアでも職種によって仕事の性質は大きく異なり、向き不向きがあります。「職種を変えたら激務だと思わなくなった」というケースも少なくありません。ただし、職種が変われば求められるスキルも一新されるため、相当な勉強量を覚悟する必要があります。
【3】心機一転したいなら、常駐先の変更
SESエンジニアの場合、心身が疲弊するほど過酷な現場であれば、常駐先の変更を視野に入れましょう。激務でどうにもならない状況では、我慢していても状況が悪化するだけ。特に炎上プロジェクトに投入された場合はなおさらです。このようなときは自ら担当営業に申し出て、事態の深刻化を防ぐことが重要です。常駐先が変わることで、人間関係や業務内容をゼロから覚え直す必要はありますが、新しい業務知識を取り入れることで、リフレッシュやスキルアップにもつながります。
なお、常駐先の変更は自身の意思だけで決められるものではありません。必ず担当営業に相談し、適切な手続きを踏んだうえで検討するようにしましょう。
【4】根本的な解決策はこれ!働きやすい企業への転職
これまでの解決策を試しても激務が改善されない場合、あるいは根本的な解決を求めるなら、転職が最も確実な方法です。例えば、以下のような特徴を持つ企業を選ぶことで、激務を根本から回避できる可能性があります。
- 案件選択の自由度が高い企業:炎上プロジェクトや自分に合わない案件を避けられる
- エンジニアファーストの企業文化:無理のない働き方を選択できる
- 充実したサポート体制:一人で抱え込まずに済む環境
- 透明性の高い評価制度:頑張りが正当に評価される
転職は大きな決断ですが、「このまま消耗し続けるか、環境を変えて再スタートするか」を天秤にかけたとき、後者を選ぶ勇気も必要です。この決断は決して“逃げ”ではありません。エンジニアとしてのキャリアを守り、長く活躍するための戦略的な選択なのです。
FAQ:エンジニアの働き方についてのよくある質問
Q1. エンジニアはみんな激務なの?
A1. 必ずしもそうではありません。確かに、IT業界には激務になりやすい要因が多く存在します。しかし、すべてのエンジニアが激務なわけではなく、働きやすい環境で活躍している人もたくさんいます。大切なのは、自分に合った働き方や企業を見つけることです。
Q2. SESエンジニアならではの大変さはありますか?
A2. SESは、現場が変わるたびに人間関係や業務内容をリセットしなければならないため、精神的な負担を感じやすい一面はあります。しかし、多くの現場を経験でき、スキルや知見を効率的に得られるメリットもあります。重要なのは、案件選択の自由度が高く、希望を伝えやすい企業を選ぶことです。
Q3. 未経験からエンジニアを目指すのは危険?
A3. 未経験からでもエンジニアになることは十分に可能です。しかし、激務を避けるためには企業選びが非常に重要になります。研修制度が充実しているか、エンジニアファーストの文化があるか、サポート体制は整っているかなどを事前にしっかり確認しましょう。
Q4. エンジニアの激務を改善するにはどんな方法がありますか?
A4. 業務効率化、職種変更、常駐先変更、転職の4つの方法があります。まずは業務効率化から始めて、それでも状況が変わらない場合や、根本的な解決を求める場合は、職種や働く環境を変えることを検討してみましょう。
Q5. 激務を理由に転職するのは「逃げ」でしょうか?
A5. いいえ、決して逃げではありません。激務によって心身を壊してしまっては、長期的なキャリア形成に支障をきたします。転職は、自身の健康とキャリアを守るための戦略的な判断です。
まとめ:「エンジニアの激務は当たり前」ではない
エンジニアが激務に悩まされる理由は、継続的な学習の必要性から炎上プロジェクトへの投入まで多岐にわたります。しかし、これらの課題は決して解決不可能なものではありません。
重要なのは、「激務は当たり前」という固定観念から脱却することです。業務効率化、職種変更、常駐先変更、そして転職──あなたには必ず選択肢があります。
どの方法を選ぶにせよ、まずは最初の一歩を踏み出さなければ始まりません。理想の働き方を諦めず、自分に合った解決策を見つけて、充実したキャリアを築いていきましょう。
IDHでは、エンジニアが自分らしく働ける環境づくりに取り組んでいます。
案件自由選択制で理想の働き方を実現したい方は、ぜひお気軽にご相談ください。



