エンジニアの仕事はつらいのか。AI時代でも変わらない真価
2021/06/29
【完全版】エンジニアの目標設定とSMART活用法|評価もキャリアも伸ばす具体例付き
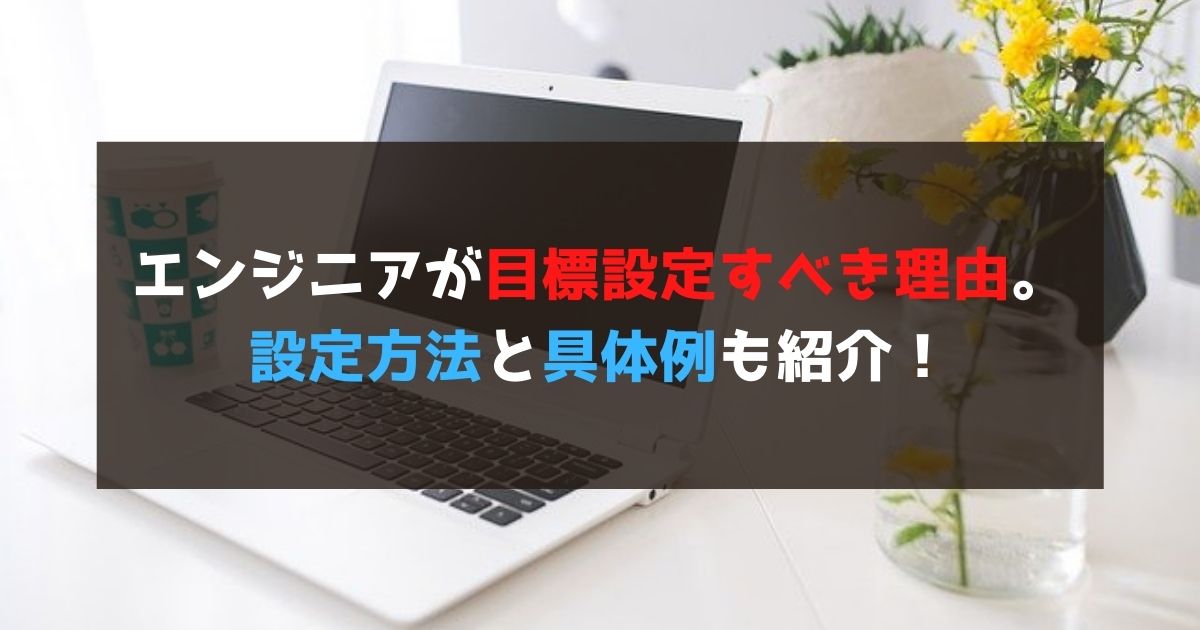
Last Updated on 2025年10月28日 by idh-recruit
エンジニアとして働いていると、「来期の目標、どう書こう……」と悩むことがありますよね。 AIやクラウドの進化が速い今、「与えられた仕事をこなす」だけでは評価されにくい時代になりました。
だからこそ「どんなスキルを伸ばしたいか」「どんな価値を生みたいか」を自分の言葉で描くことが大切です。 それが、変化の早い現場で自分を見失わないための「軸」になります。
この記事では、エンジニアが目標を立てるときの考え方と、すぐに使える具体例・書き方のポイントを紹介します。 会社提出用の目標と、自分のキャリアを伸ばすための目標、両方の観点から整理していきましょう。
Contents
なぜエンジニアは目標を立てるべきなのか

「毎日、目の前の仕事をこなすだけで精一杯……」 そんなふうに感じたこと、ありませんか?
ITエンジニアの世界は技術の移り変わりが速く、数年で「当たり前」が変わります。 だからこそ、「自分は何を伸ばしたいのか」「どんなエンジニアになりたいのか」を言葉にしておくことが、成長を続けるうえでの「軸」になります。
① 成長スピードが速い業界だからこそ「軸」が必要
生成AIやクラウド自動化の普及で、仕事の進め方が大きく変わりました。 自分の方向性を決めずに動くと、気づけば周りとのスキル差が広がることも。
目標を立てておくことによって、どんな変化の中でも「何を優先すべきか」が見えやすくなります。
② 評価・チャンス・報酬につながる
最近は評価制度でも、「どんな成果を出したか」だけでなく「どんな意図で動いたか」が重視されています。 「今期はAWS運用を自動化できる仕組みを作る」など、具体的な目標を掲げて行動することで、評価につながりやすくなります。
③ 行動が変わり、結果が見える
目標を立てると、自然と「逆算思考」になります。 「目標を達成するために今日何をするか」を考えるようになり、行動が具体化していくのです。 結果としてスキルも成果も可視化され、成長実感が得やすくなります。」「
④ 自信とモチベーションにつながる
小さくても「できた」という経験を積み重ねると、自信が生まれます。 この前向きな循環が次の挑戦を後押ししてくれます。 最初は「仕事の宿題」のように感じてしまって億劫かもしれませんが、続けるうちに「成長の足あと」として振り返られるようになります。
会社の評価用目標と、自分のキャリア目標の違い
目標を立てようとすると、まず理解したいのが「目標と目的は違う」という事実。 会社に入って「今期の目標を提出してください」と言われると、つい「数字を埋めること」や「評価されること」が目的になってしまいがちですよね。
でも、本来の目的は「自分がどんなITエンジニアになりたいのか」を形にすること。 いったん立ち止まって、「何のためにその目標を立てるのか」を思い出してみましょう。
会社から求められる「評価用目標」
会社が求めるのは、組織として成果を出すための「行動指針」です。 たとえば「納期遵守率を上げる」「工数を削減する」「コードレビューを定着させる」など、チームの成果に直結する内容が求められます。
こうした目標は、「どんな価値をチームや顧客に提供できるか」という視点で書くと伝わりやすく、上司の評価基準も明確になるでしょう。
一方で、自分の「キャリア目標」は未来の自分への約束
キャリア目標は、今の仕事の「先」を見据えて立てるもの。 「3年後にマネジメントに挑戦したい」「クラウド設計を任せられるレベルになりたい」など、自分の理想像を描くための道しるべです。
この目標があることで、目の前の業務にも意味づけができ、日々の努力が「成長の積み重ね」として感じられるようになります。
両方を意識して書くとブレない
- 会社の目標 → 「組織にどう貢献するか」
- キャリアの目標 → 「自分がどう成長したいか」
この2つをセットで考えると、「上司のため」でも「自分の理想だけ」でもない、現実的で納得感のある目標になります。
たとえば、
- 会社の目標:AWSの運用効率を上げる自動化フローを構築する
- キャリア目標:クラウドインフラの設計段階から提案できる力を身につける
こう書くと、評価と自己成長の両方が一本の線でつながります。
まとめ
目標とは、数字を埋める作業ではなく、「目的(何のためにやるか)を可視化するツール」です。 だからこそ、一度立ち止まって「自分は何を目指しているのか」を思い出す――そのひと手間が、形だけの目標を「意味のある目標」に変えてくれます。
SMARTの法則で目標を立てる
「いい目標を立てよう」と思っても、いざ書こうとすると「ふわっとした理想」で止まってしまうこと、ありますよね。
そんなときに役立つのが、SMART(スマート)の法則です。
SMARTとは?―世界中の企業が採用する「目標設定の基本」
SMARTの法則は、1981年に経営学者ジョージ・T・ドランが提唱した目標設定のフレームワークで、現在も世界中の企業が採用しています。IBM等の企業でもその有効性が言及されています。
| S:Specific(具体的に) 「何を」「どのように」行うのかを明確にする。 例:「資格を取る」ではなく「AWS SAA資格を3か月以内に取得する」 | M:Measurable(測定可能に) 数字や期間で、達成を判断できるようにする。 例:「3件」や「10%」など、ゴールが見える形に。 |
| A:Achievable(達成可能に) 無理のない範囲で、現実的に設定する。 例:現職の業務時間・スキルを考慮して設定。 | R:Relevant(関連性を持たせる) 会社やキャリアの方向性と結びつける。 例:チーム貢献や自身の成長に関連づける。 |
| T:Time-bound(期限を決める) いつまでに達成するかを決める。 例:「半年以内」「今期末まで」など期限を明記。 | |
SMARTを使うときのコツ
ポイントは、「一度に完璧に作らなくていい」ということ。 まずはざっくり書いてから、SMARTの5つの視点で少しずつ整えていきましょう。
Before(あいまいな目標)
クラウドスキルを上げたい。
After(SMARTで整理)
3か月以内にAWS SAA資格を取得し、本番環境のインフラ設計レビューに参加できるようになる。
これだけで、「行動の方向」と「期限」がはっきり見えるようになります。
「やる気を持続させるための仕組み」としてもSMARTは有効と言えます。
| フェーズ | 目標例 | やること |
|---|---|---|
| 新卒/1年目 | 3か月以内に自分で環境構築ができるようになる | 先輩の開発環境をまねて構築し、週1で復習メモを残す |
| 3年目/中堅層 | 半年でコードレビューの主担当を担う | ペアレビューを月5回行い、品質指標を共有 |
| リーダー層 | チームのリリーススケジュールを3か月前倒しで達成する | メンバーの進行状況を可視化し、週次ミーティングを改善 |
SMARTの法則はキャリアステージを問わず活用できます。
むしろ経験が増えるほど、「自分の目標を他者と共有できる言葉にする」力が問われるようになるため、キャリアを伸ばすうえでも積極的に取り入れたい考え方です。
まとめ
SMARTの法則は、理想を「行動に変えるための整理術」です。 抽象的な目標をひとつずつ具体化していく。 それだけで「何をすべきか」明確になり、自然と次の行動が見えてきます。
次の章では、実際に職種別の具体例(SE/インフラ/Web等)を見ながら、自分に合った目標を立てるステップに進みましょう。
職種別|エンジニアの目標設定具体例
ここまでで、「目標を立てる意味」と「SMARTで形にする方法」はつかめたと思います。でも実際に書こうとすると、「自分の職種だと、具体的にどんな書き方がいいのか?」と迷いますよね。
ここでは、ITエンジニアの主要5職種を例に、評価用目標(会社提出向け)とキャリア目標(自分の成長軸)の両方をセットで紹介します。
SE(システムエンジニア)
評価用目標(組織貢献)
要件定義段階でのレビュー体制を整備し、再修正工数を前期比20%削減する。
キャリア目標(自己成長)
要件定義〜設計〜レビューの一連を主導できるリーダーシップを身につける。
システムエンジニアは、プロジェクト全体を見渡す「設計の要」。現場の課題を拾い上げつつ、改善施策に落とす姿勢が評価につながります。
「数字で見える改善」と「自分がどう成長したいか」を両立させるのがポイントです。
インフラエンジニア
評価用目標
Terraformを導入して、手動構築作業を半期で50%削減する。
キャリア目標
クラウドインフラを設計段階から提案できるアーキテクトスキルを磨く。
自動化や可観測性の向上など、「地味だけど効く改善」が多いのがインフラ領域。 SMARTの「Measurable(測定可能)」を意識して、「どの作業をどれくらい削減できたか」を明文化すると説得力が増します。
Web/フロントエンドエンジニア
評価用目標
サイト全体のCore Web Vitalsを改善し、CLSを0.1以下・LCPを2.5秒以内に保つ。
キャリア目標
デザインやUX観点も踏まえた改善提案ができる「フロント+体験」エンジニアになる。
Web系は、数字で改善効果を示しやすい分野です。パフォーマンス指標(速度・安定性)をKPIに設定し、「技術でユーザー体験を良くする」という観点を入れると評価が上がりやすくなります。
若手エンジニア(1〜3年目)
評価用目標
チームのコードレビューに週1回以上参加し、指摘内容を記録・共有する。
キャリア目標
毎月1テーマを決めて自主学習し、社内LTやブログでアウトプットする。
最初のうちは「習慣化」を目標にするのが効果的です。 「スキルを広げる」よりも「学び続ける習慣をつくる」ほうが長期的には強いからです。小さな実践を積み重ねることで、のちのキャリア目標が具体化していきますよ。
リーダー層・マネジメント
評価用目標
コードレビュー基準をチームで統一し、品質チェックの属人化を解消する。
チームメンバーの進行状況を可視化し、リリース遅延率を前期比30%削減する。
キャリア目標
チーム全体の生産性を支える「仕組み設計」ができるマネージャーを目指す。
マネジメント層では、「自分の成果」より「チームの成果」をどう高めるかが焦点。 個人KPIではなく、チームのKGI(目標成果指標)を設定すると、「管理ではなく支援」というリーダー像が伝わります。
まとめ
目標を立てるときに大事なのは、「自分ができること」ではなく「自分がどうありたいか」を軸に置くこと。
数字やスキルは通過点にすぎません。 どの職種でも、SMARTの5要素と「評価 × 成長」の2軸を意識すれば、形だけで終わらない「生きた目標」になります。
目標を達成するための習慣・振り返りのコツ
目標を立てた瞬間は「よし、やるぞ」と思えても、忙しい日々の中でだんだん意識が薄れていくことありますよね。 でも、少しの工夫で「続ける仕組み」をつくることはできます。
ここでは、日々の習慣づくりと、成長を実感するための振り返りのコツを紹介します。
1. 「時間を決める」より「タイミングを決める」
「毎朝1時間勉強する!」と決めても、予定がずれると続かなくなりがち。
それよりも、「きっかけ」で行動できるようにすると続けやすくなります。
たとえば:
- 通勤電車に乗ったら技術記事を1本読む
- 朝のコーヒーを淹れたら昨日のメモを見返す
- デプロイが終わったら学びをSlackに投稿する
こうした行動トリガーを決めることで、意志ではなく仕組みで続けられるようになります。
2. 「1週間単位」で小さく区切る
1か月や四半期単位で考えると、成果が見えにくくなります。
週単位で「今週できたこと」「できなかったこと」を振り返る方が、スモールステップの積み重ねが実感しやすいです。
たとえばエンジニアなら:
- 今週はAWS CLIを触って小さな自動化を試した
- テストコードの書き方でつまずいたけど、来週リトライする
こうして「成功も失敗も同じ目線で記録」していくと、学びのログがたまって自信につながります。
3. アウトプット前提で学ぶ
学びを定着させる一番の方法は、誰かに話すこと・書くことです。ブログ、社内チャット、勉強会LTなど、形式は何でも構いません。
人に伝える前提でインプットすると、自然と理解が深まり、「どう説明すれば伝わるか」を考える癖がつきます。
成長は、「学んだ量」ではなく「伝えた回数」で実感できる。
この意識を持つだけでも、日々のモチベーションが変わりますよ。
4. 「達成したかどうか」より「何を得たか」で振り返る
目標が100%達成できなくても、それ自体は問題ではありません。 大切なのは、そこまでのプロセスで何を学べたかです。
たとえば:
- AWS資格には落ちてしまったけど、VPC構成の理解が深まった
- コードレビューの基準作りは途中だが、議論の文化が定着した
結果より「成長の中身」を言語化することで、次の目標がよりリアルで自分らしいものになります。
5. 定期的に「軸」を見直す
環境や立場が変わると、目標の意味も少しずつ変化します。 「今の自分に合っているか?」を定期的に見直す習慣を持つと、形だけの目標ではなく、「進化する目標」になります。
3か月に一度、過去の目標を見返してみましょう。 書いたときには見えなかった成長や、新しい課題に気づくはずです。
目標は「変えてはいけない」ものではなく、「進化させる」もの
目標を達成する力は、気合いではなく習慣でつくられることがわかったと思います。
- 行動のトリガーを決める
- 小さく振り返る
- 学びを発信する
- 結果より成長を見つめる
- そして定期的に軸を更新する
最後に、もう一つ大切な考え方をお伝えします。
目標が達成できない人に共通する3つの落とし穴
どんなに良い目標を立てても、「うまくいかない」と感じる時期は誰にでもあります。そのとき大切なのは、「自分がダメ」と思うことではなく、つまずきやすいパターンを知ること。ここでは、目標が達成できない人に共通する3つのポイントを紹介します。
① 目標が高すぎて現実味がない
「せっかくだから大きな目標を立てたい!」
――そう思う気持ちは素晴らしいのですが、あまりに高すぎる目標は「やる気の持続」を奪います。
たとえば、現時点でインフラの基礎を学んでいる段階で「半年以内にAWS認定プロフェッショナルを取る」など、現実とのギャップが大きいと途中で「無理かも」と感じてしまいがちです。
理想を描くことと、現実的なステップを設定することは別の話。
まずは「小さく達成できる成功体験」を重ねて、少しずつハードルを上げていきましょう。
🎯 コツ:高すぎる目標よりも、「今の自分より半歩先」を目指す。
② 「自分ごと化」されていない目標
他人に決められた目標や、上司に言われて仕方なく書いた目標は、どうしても「やらされ感」が強くなります。
モチベーションを維持するためには「なぜそれをやりたいのか」という「自分の中の理由」が必要です。
たとえば同じ「資格を取る」という目標でも、
- 「評価に必要だから」よりも
- 「自分の設計力を証明したいから」
といった自分の言葉で動機づけるだけで、行動の質が変わります。
💡 コツ:他人に説明する前に、「自分のための理由」を一行メモしておく。
③ 立てただけで「行動の仕組み」がない
目標を立てて満足してしまい、行動に移せない―― 実はこれが、最も多いパターンです。
行動につなげるためには、「何を・いつ・どの順でやるか」をざっくりでもロードマップ化しておくことが大切。
たとえば、
- 1か月目:公式ドキュメントを読む
- 2か月目:ハンズオンを1つ完了
- 3か月目:模擬試験を受けて弱点を分析
といったように、行動の地図を描いておくと迷いにくくなります。
🗺️ コツ:「目標 → タスク → 日々の行動」に分解する。
目標変更は「敗北」ではなく「再調整」
3つの落とし穴に気づいたけど今更目標変更できない……そんな風に思った方もご安心ください。
現場で働いていると、技術トレンドも業務環境も想定以上の速さで変わります。その中で、当初の目標が現実に合わなくなることは自然なこと。
むしろ、「状況に応じて見直す力」こそが、成長を止めないための武器です。
たとえば次のような工夫を取り入れてみてください。
- 四半期ごとに目標の棚卸しを行う(例:新技術やチーム体制の変化に合わせて再設定)
- 変更理由を記録し、上司やチームで共有する(透明性と納得感を保つ)
- 承認フローを簡素化して「柔軟な再設定」を許可する(形式よりも成長の継続を優先)
これにより、「計画通りにいかなかった」ではなく、「今の自分とチームに合わせて最適化した」と捉えられるようになります。
まとめ|目標は「努力の宣言」ではなく「成長の設計図」
エンジニアの目標設定は、スキルアップのためだけでなく、自分の軸を見失わずに成長し続けるための道しるべです。
目標を立てるときは、
- 自分にとって意味があるか(Will)
- 会社やチームに貢献できるか(Value)
- 現実的に達成できる範囲か(Do)
を意識してみましょう。
そして、立てて終わりではなく、小さくても行動し、定期的に振り返り、また次の一歩を描く。 そのサイクルを回すことが、確かなスキルアップにつながります。
目標は、「努力しなければならない」義務ではなく、「どんな自分になりたいか」を可視化するツールです。
焦らず、比べず、ひとつずつ積み重ねていきましょう。 気づけばその足あとが、あなた自身のキャリアを形づくっています。
\ 目標設定に悩むエンジニアを全力サポート /
「自分に合った目標が分からない」「キャリアの方向性を相談したい」
そんな方は、IDHのキャリア相談をご活用ください。
経験豊富なアドバイザーが、あなたの成長をサポートします。
新着ブログ
未経験からインフラエンジニアになるロードマップ【転職までの詳細ステップ】
ITエンジニアに営業力は必要?売り込みではない価値化スキルを解説
Java初心者が挫折しない勉強法|独学・教材・レビュー活用のベストプラン
Webエンジニア3年目で年収を上げるには?転職・スキル戦略を解説
エンジニア3年目で「向いてない」と感じるのはなぜ?レベル・スキル・転職の判断基準
JavaScriptとは?できること・作れるもの、難易度、基本文法などを初心者向けに解説
ITパスポートとは?取得するメリット・難易度・向いている人を解説
エンジニアのコミュニケーション課題とは?原因と改善方法をわかりやすく解説



