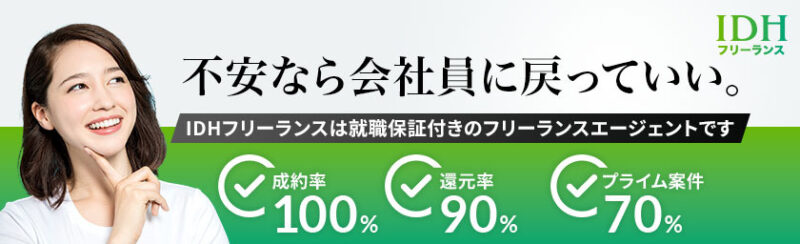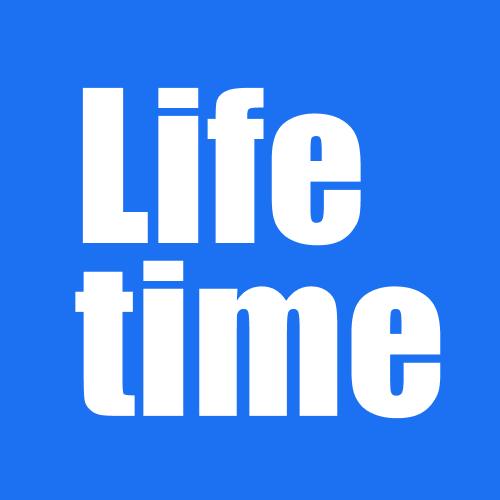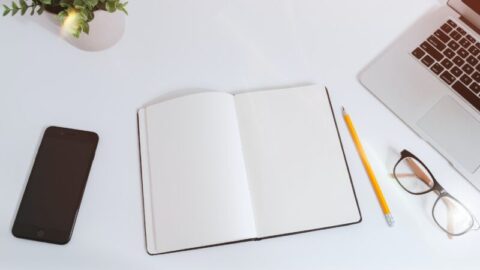話すのが苦手なエンジニア必見|伝え方のクセを知るだけでコミュニケーション激変

エンジニアは最先端の技術や高度な専門知識を駆使して課題を解決する一方で、「話がスムーズに伝わらない」「会話が噛み合わない」という、コミュニケーション問題に直面することが少なくありません。実際エンジニア同士だけでなく、非エンジニアとのやりとりにおいても、その「伝わらなさ」が原因で誤解やすれ違いが生じてしまうケースが散見されます。
しかしこうした問題の根底には、「伝え方のクセ」ゆえに相手にとってわかりにくい説明になってしまうという現実があります。本記事ではなぜエンジニアが「話すのが苦手」と感じるのか、その原因となる認知やクセを明らかにします。誰でもすぐに実践できる「円滑なコミュニケーション」への小さな一歩を提案しますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
1.“話すのが苦手”なエンジニアは意外なほど多い

「エンジニアって、なんか話が通じないよね」──
そんな言葉をネットや職場で耳にしたことがあるかもしれません。面と向かって言われたことはなくても、どこか心当たりがあってモヤッとした経験、ありませんか?実はこの“伝わらなさ”は、エンジニアという職業特有の思考スタイルや話し方が影響していることが多いんです。
たとえば――
- 普段使っている専門用語や略語が非エンジニアにはなかなか通じない
- 論理的に説明しようとするあまり、細かい工程や背景まで丁寧に話してしまう
- 問題を冷静に分析して返答するうちに、「皮肉っぽい」「冷たい」と受け取られてしまう
- 相手の話の途中で解決案を提示してしまい、「最後まで聞いてくれない」と誤解される
- 感情よりも事実を重視する態度が、「無関心」「非協力的」と映ることもある
加えてリモートワークの普及によって「会話の空気感」や「細かい表情のニュアンス」が伝わりにくくなり、話すのが苦手だと自覚している人にとっては向かい風となっています。どれもエンジニアとしてまっとうに仕事をしているつもりなのに、相手からは“話しにくい人”と見られてしまう……そんなすれ違いが日常的に起きているのです。
でも、これらはあなたの“性格のせい”ではありません。このあとのセクションでは、こうした「伝え方のクセ」がどこから来ているのか、そしてどうすればすれ違いを減らせるのかを一緒に探っていきましょう。
2.「伝え方のクセ」って何?──認知のズレに気づく
なぜ「コミュニケーションが難しい」と感じる場面が生まれてしまうのでしょうか?その背景について解説していきます。
話が伝わらないのは思考の“クセ”による詰まり
コミュニケーションがうまくいかないとき、つい「話すのが下手だからだ」「自分は説明が苦手なんだ」と自分にダメ出ししてしまうことがあります。でも実際には“話し方”そのものよりも、思考パターンがそのまま言葉に現れていること=クセが原因で、うまく伝わらないケースが多いのです。
エンジニアとして日々正確で論理的な思考を求められているあなたならなおさら、普段通りに考えて話しているだけで、相手との“認知のズレ”が生まれやすくなっている可能性があります。
「主語がない」「説明の順序が逆」など。よくあるパターン
具体的にどんなクセが“伝わらなさ”につながっているのでしょうか。代表的なパターンは以下のようなものです。
- 主語が抜けている
例:「やる必要があります」→誰が?何を?が不明確
- 抽象的な概念から話し始める
例:「ここの非同期処理が非効率で……」→相手は“何の話?”となる
- 説明の順序が逆になっている
例:「この処理はA→B→Cで動いていて…」→結局何が問題なのかが見えにくい
こうしたクセは、本人にとってはごく自然な話し方なのに、聞き手には「何が言いたいの?」「わかりにくいな」と感じさせてしまいます。
コミュニケーションは性格の問題ではない
ここで大事なのは、「これらは性格の問題でも努力不足でもない」ということ。
伝え方にクセがあるのは、あなたが普段から鍛えてきた“論理的な思考スタイル”が無意識に言葉に出ているだけなのです。つまり「話すのが苦手」なのではなく、“伝わる順序や言い回し”に慣れていないだけ。少しだけ調整すれば、驚くほど伝わり方が変わっていくでしょう。
次のセクションでは、その「最適化」の方法を具体的にご紹介していきます。
3.エンジニアのコミュニケーションを最適化する具体的な方法

エンジニアとして高い技術力を持つことは重要ですが、コミュニケーション能力も同様に重要です。
「話すのが苦手」と感じていたとしても、伝え方にちょっとした工夫を加えるだけで周囲とのやりとりがスムーズになることがあります。つまり、コミュニケーションは“最適化”できるスキルなんですね。
ここからは、現場で今日から試せる具体的な改善ポイントを見ていきましょう。
専門用語を噛み砕いて説明する
非エンジニアと技術的な話をする際は、専門用語や略語をそのまま使うのは避けましょう。
「このAPIはRESTfulで、JSON形式のレスポンスを返します」と説明しても、相手は理解しづらいです。この場合、「この仕組みは他のサービスと情報をやり取りできて、結果は読みやすい形式で返されます」といったように、相手の知識レベルに合わせて噛み砕いて説明しましょう。
共感の意識を持つ
相手の立場や感情に寄り添うことで、信頼関係を築くことができます。
ライアントがシステムの不具合で困っている場合、「それは大変でしたね。早速対応策を考えましょう」と共感の言葉を添えることで、相手は安心感を持ちます。相手の感情を無視せず、相手の気持ちを理解しようとする姿勢が重要です。
フィードバックは建設的に
問題点を指摘する際は、否定的な表現を避け、改善策を提案するようにしましょう。
たとえば、「このコードは全然ダメです」ではなく、「この部分をこうするともっと効率的になります」と伝えると、相手も受け入れやすくなります。建設的なフィードバックは、チーム全体の成長にも繋がるでしょう。
情報共有は積極的に
自分の作業状況や問題点をチームに共有してミスコミュニケーションを防ぎましょう。
「話したところでエンジニア以外にはわからないから意味がない」などと自分だけで黙々と作業を続けることは避けてください。週次ミーティングで進捗報告を行ったり、問題が発生した際にすぐに相談したりすることでチーム全体の効率が向上しますし、チームとしての一体感が生まれます。
フリーランスなら特にコミュニケーション重視
フリーランスエンジニアの場合、コミュニケーション能力は技術力と同じぐらい重要になります。クライアントとの信頼関係が直接、仕事の継続や新規案件の獲得につながるからです。
これからフリーランスとして独立する、またはすでに独立しているエンジニアは次のような点に注意しながらコミュニケーションを取りましょう。
・要件の明確化
初期段階でクライアントの要望をしっかりとヒアリングし、不明点はその都度確認しましょう。たとえば、「この機能はユーザーがどのように使うことを想定していますか?」と具体的に質問をすることで、ミスを防げます。
・定期的な進捗報告
プロジェクトの進行状況を定期的に報告することで、クライアントに安心感を持ってもらえます。報告内容は簡潔に、しかし必要な情報は漏れなく伝えましょう。
・素早いレスポンス
問い合わせや連絡に対して迅速に対応することで、信頼度が高まります。忙しい場合でも、受領した旨を一報入れるだけで相手の不安を和らげることができます。
・プロフェッショナルな態度
「納期は必ず守る」「契約内容を遵守する」など、基本的なビジネスマナーを徹底しましょう。問題が発生しそうな場合は早めに連絡し、代替案を提案することが大切です。
>>IDHフリーランスは、就職保証付きで“戻れる安心”があるエージェントサービスです。
4.明日から使える!“伝わる伝え方” 実践チェックリスト
ほんの少し話し方の順序を変えたり前提を意識したりするだけで、伝え方は驚くほど改善できます。このセクションでは、そんな「すれ違いを減らすためのヒント」をチェックリスト形式でまとめました!
✅ 話し方の順序の見直し
話し始めは「結論」から伝えるようにしている
背景や理由はあとから、必要に応じて補足している
✅ 相手との認識ズレを防ぐ工夫
専門用語を使うときは、ひと言補足するようにしている
「これって通じるかな?」と考えてから話すようにしている
会話の途中で「ここまで大丈夫そうですか?」と確認している
✅ “可視化”を味方につける
複雑な内容は図や箇条書きにして説明している
話す前に紙に書いて頭を整理している
✅ フィードバックや指摘の伝え方に気を配る
「ダメです」ではなく「こうすると良くなる」と伝えるようにしている
感情やちょっとした雑談も、必要に応じて添えている(事務的すぎるやりとりにならない工夫)
✅ 自分の「伝え方のクセ」に気づく意識を持つ
主語を省略しないように気をつけている
「なぜその話をしているのか」を意識しながら話すようにしている
ひとつでも「できてないかも……」と感じた項目があれば、そこが改善の入り口。完璧を目指す必要はありません。まずはできそうなことを1つだけ、今日の会話で試してみる──それがスタート。伝え方は“センス”ではなく“工夫”。あなたに合ったスタイルを少しずつ見つけていきましょう。
5.非エンジニアとのコミュニケーションで戸惑ったら──エンジニアとしての対処法
エンジニアとして働いていると、非エンジニアとのやりとりの中で「うまく伝わらない」「話が噛み合わない」と感じる場面に出くわすこと、ありますよね。それはあなたの話し方が悪いのではなく、立場や知識の前提が違うことによる“すれ違い”が原因かもしれません。
本来、コミュニケーションはどちらか一方の努力で成り立つものではありません。エンジニア側が少し工夫することで、相手の理解を助けたり、こちらの状況を伝えやすくすることはできますが、最終的には「お互いの歩み寄り」があってこそ対話はスムーズになります。ここではエンジニア側の視点で「よくあるギャップ」を整理しながら、コミュニケーションをスムーズに進めるための工夫をご紹介します。
抽象的な要望には、具体化のための質問を返す
「もっとユーザーフレンドリーにして」「もう少しデザインをカッコよく」
──こんなふんわりした依頼に戸惑った経験、ありませんか?
非エンジニアの多くは感覚的に物事を伝えようとするため、抽象的な表現になりがちです。そんなときは、こちらから具体的に確認してみるのがポイント。たとえば「“ユーザーフレンドリー”というのは、ボタンの色や配置、文字サイズなど、具体的にどこが気になりますか?」このように相手の言葉を咀嚼してあげることで、意思疎通がグッとしやすくなりますよ。
無理な依頼には、理由を添えて“相談ベース”で返す
「この修正、明日までにいける?」
そんな無茶振りをされて、内心「いやさすがに無理だろ……」と思ったとしても、そのまま返すのではなく相談ベースで返すとその後の会話も続きやすくなります。「できない」と突き放すのではなく、制約や必要工数を説明して共に着地点を探る姿勢がポイント。
たとえば「この機能は設計と検証を含めて2~3日必要です。急ぎであれば、まずA部分だけ先に対応する方法もあります」こういった“相談ベース”の伝え方に変えるだけで、非エンジニアの相手も納得しやすくなり、双方のコミュニケーションが円滑になるんです。
モヤっとする言い方には、丁寧な問い直しで対応
「なんか使いにくいんだけど」「うーん、ちょっと違う気がする」
非エンジニアからのふわっとしたフィードバックにどう返すか、悩むこともあるかと思います。ここで大切なのは、「なぜそう感じたのか」を掘り下げて聞いてみること。たとえば「どの部分でそう感じたか、具体的に教えてもらえますか?」など。質問の仕方を工夫するだけで、相手も考えを整理しやすくなり素直な意見を返してくれることがあります。
非エンジニアとのコミュニケーションで生まれるギャップ。大半はお互いの認知や前提のズレが原因です。だからこそエンジニアとして「伝え方を少し工夫する」ことがすれ違いを防ぐ一番の近道に。もちろんできることからで大丈夫。それだけでチームの空気も軽くなっていきますし、仕事もやりやすくなりますよ。
6.まとめ|伝わるエンジニアになるために

話すことに苦手意識を持つエンジニアは少なくありません。でもそれは“あなたが話し下手だから”でも、“コミュ力が足りないから”でもないのです。
本記事で触れてきたように話が伝わらない原因の多くは、「思考スタイルがそのまま言葉に出ている」というだけ。つまり、自分の中では筋が通っていても、相手には伝わりづらい形になってしまっている──ただそれだけなんです。
IT人材転職サービス『ウィルオブテック』が2022年に全国の採用決裁者100名に行った調査では、中途ITエンジニアの採用時に最も重視されるスキルとして「コミュニケーションスキル」が60%で1位という結果が出ています。
つまり、技術力以上に一緒に働ける人かどうかが見られているということ。
「話すのが苦手だから」と放置しておくと、転職やキャリアアップのチャンスそのものを逃してしまう可能性もあるのです。コミュニケーションの仕方を少しずつ整えていくことは、未来の選択肢を広げる“投資”とも言えるんですよ。
理想の働き方を、もう諦めない!
IDHはあなたの強みや価値観に寄り添い、最適なキャリアパスをサポートします。今の環境に少しでもモヤモヤを感じるなら、まずは気軽に相談してみませんか? ⇒ 【IDHであなたの可能性を探る】

エンジニアに求められるコミュニケーション能力とその向上方法とは?
エンジニアに求められるコミュニケーション能力とは?【Lifetime Engineer】では仕事上でのコミュニケーションが上手くいかないことに悩んでいるエンジニアの方に向…

【もしかして必須?】ITエンジニアに営業力は必要なのか?
エンジニアに営業力は必要なのでしょうか。 この点、一般的には不要だと思われがちですが、「エンジニアにも営業力は欠かせない」との話もあります。 ここでは、エンジニアに営業力…

フロントエンドエンジニアはつらい?よくある悩みと打開策、転職、キャリアチェンジについて解説
フロントエンドエンジニアはなぜつらい?【Lifetime Engineer】では、フロントエンドエンジニアの実態や働き方に興味がある方に向けて、フロントエンドエンジニアが…